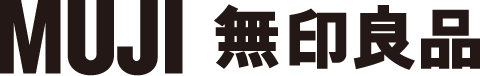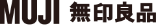小高ワーカーズベース 和田智行さん
小高駅通り、双葉屋旅館よりもさらに駅寄りの場所に小高ワーカーズベースはある。小高ワーカーズベースは、2014年5月に立ち上げられた事業で、「目指しているのは、小高区に帰還する、または帰還を検討している住民の暮らしを支えるビジネスの創出」(「小高ワーカーズベースについて」より)とのこと。
小高ワーカーズベースの業務内容は、コワーキングスペースの創設、小高初となる食堂「おだかのひるごはん」のオープン(現在はクローズ)、仮設スーパー「東町エンガワ商店」の開設、「HARIOランプワークファクトリー小高」でのガラスアクセサリーの生産・販売など多岐に渡る。その中心にいるのが、この地で生まれ育った和田智行さんだ。小高の人たちと話をしていると、和田さんの名前が必ず出てくる。和田さんがいかに、住民の信頼と期待を集めているかがわかる。
この地でベンチャーを立ち上げることの意味、そして小高の現況と問題解決の手続きについて、和田さんにお話しを伺った。
「震災前から小高で生活をしながら、東京のITベンチャーの会社で役員の仕事を遠隔勤務でしていました。ITの世界は変化が早く、競合も多い業界なので、生き残りが大変です。ビジネスチャンスを見つけなければならず、技術も身につけていかなければならないハードな仕事なので、50歳を過ぎても続けられるだろうか、と漠然とした不安を持っていました。

和田さんが立ちあげた小高ワーカーズベース
震災後も、避難先で遠隔で仕事をしていたのですが、現在の仕事が自分に降りかかった避難者という状況に1ミリも近づけないことに徐々にストレスを感じるようになって、役員を務めていた会社を全部辞めました。それで次に何をしようかと考えた時に、ここには課題がたくさんある、と。課題ってビジネスのネタですよね。これまでビジネスチャンスを見つけるのに苦労していたのに、ここはネタだらけなんです。いずれ小高に帰ろうと思っているのであれば、この地で課題を解決するビジネスを作っていくことにはやりがいもあるし、個人としての課題解決にもつながる、と考えたんですね。
誰もこの場所でやりたがらないし、誰もうまくいくとは思っていないわけですね。僕が仕事をしていたWebの世界では、チャンスがたくさんあって、参入障壁も低くて、いろんな人が入ってくるわけですけれど、ここでは誰も何もやりたがらない。小高で生まれ育った自分が、避難先から帰還して、誰もやろうとしないこの場所で課題解決ビジネスを先駆けて行うというストーリーは、文句のつけようのないものだし、うまくいけば良い方向に動くのではないかと考えました」

ベース内で仕事をするスタッフ。小高に再び帰ったきた若いスタッフもいるとのこと
和田さんが指摘するように、この地においてはすべてが課題だ。しかし眼前に山積した課題を前に、どこから手を付けていくべきなのか。そして、それらの課題をどのようなソリューションに基づいて解決へと導いていけばいいのか。和田さんが選択したのは、まずは日常に近いレベルから仕事を始めていく、という基本姿勢だ。
「われわれ単体だけでは仕事はできないので、いろんな人に応援してもらう必要がありました。そこで、みんなが共通して実感している案件から着手することにしました。ITベンチャーを起業して、雇用を創成した方がいいのではないかという意見もありました。でもそれだと、この土地でやる意味が見いだせません。地域の課題解決に直結した、わかりやすいソリューションから入ることを心がけました。
僕は飲食店やコンビニでアルバイトをした経験はありませんが、そんな人間でも食堂やコンビニを経営できるんですね。食堂をやる時は、こんな場所でやってもうまくいかないと否定的な意見をいただきました。今この周辺で、飲食店がぽつぽつ再開しています。スーパーやコンビニも3軒オープンしました。呼び水としての役割を果たすことはできたと思っています」

スペース内に掲げられたOWB(小高ワーカーズベース)ウェイ。理念と決意の宣言文に打たれる
現在、和田さんが力をいれているのがNext Commons Lab南相馬だ。「地域リソースに対する事業創出などを目的とした、マルチセクターによる活動プラットフォーム」(「Next Commons Lab とは」より)を目指して、様々なジャンルのプロジェクトへのコミットメントを希望する起業家を募っている。最大3年間の活動支援金の支給もある。詳細はNext Commons Labのサイト(http://nextcommonslab.jp)を見ていただくとして、既存の社会・経済システムのあり方を問う実験的かつ革新的な試みには、耳を傾ける価値がある。
「募集をかけて2ヵ月と少し経ちましたけれど、現実はなかなか厳しいです。関心は高いんです。説明会には熱心な方がたくさん来られます。起業というと、どうしても高いハードルをイメージしがちです。説明会場では、そうしたイメージの払拭を心がけています。感触として、小高に起業家を呼びこむことは不可能ではないと考えています」
Next Commons Lab南相馬について調べ、説明会を訪れるのは若い世代だ。若い世代にとって魅惑的な仕事を創出する必要にも迫られている。高齢者人口の割合の増大と若年層人口の減少は、小高だけが抱えた問題ではない。日本全国の地方都市、いずれは都市部においても顕在化してくる問題である。未来の日本社会の縮図がこの地にあると言っても過言ではない。

小高の人たちの和田さんに寄せる期待は大きい
「震災によって出ていかざるを得なくなった住民のうち、避難解除後に戻ってきた人は、どうしてもここに住みたい人だけです。田舎には、都会に出ていきたいけれど仕方なく住んでいる層が一定数いますが、ここには本当に住みたい人しか暮らしていません。彼らの多くは年配者ですが、この地域を何とかしたいと思っています。だけれど、振り絞る体力も気力もない。そこで、僕らのような若い世代が行動を起こすと、応援してくださるんですね。コミットメントへのモチベーションが高い人が多いのが、元避難区域だった町の特徴と言えるかもしれません。
一方で、若い世代の中には、安定的な収入を確保したい層はもちろんたくさんいますけれど、収入よりもやりがいやコミュニティへの参加度に比重を置く人たちが増えている気がします。彼らには、コミットメント意識の高い地域の人たちの応援を仰ぎながら、ここでチャレンジできる場所を提供したいです。おっしゃるように、小高はこれからの日本が直面する課題を数十年も先取りしている場所です。ここでの解決プロセスを1つのモデルとして、全国に広められる可能性も期待できます。
安定的な生活は誰もが望むことです。だから大企業への就職希望者が多い。だけれど今の世の中、大企業に勤めたからといって、生活が保証されるわけではありません。誰もが知っている一流企業が、突然倒産しうる時代です。今年の夏は西日本でも甚大な自然災害がありました。100パーセント安心、安全な場所はありません。どのような環境の変化にも対応して、その環境の中に価値を見いだしていく力をつけることが、長期的な目で見たら最大の安定と言えるのではないでしょうか。大企業に勤めるよりも、ローカルな場所でいろいろな事案にぶつかりながらチャレンジすることが、豊かな人生をもたらしてくれる場合もあるのです」
和田さんの言葉は、小高という土地の事情を抜きにしても、若い世代へ向けてのキャリアデザインの提案として多くの示唆を含んでいる。小高の地に種を蒔き続ける和田さんにとって、プロジェクトのゴールはどのようなものとしてイメージされているのだろうか。
「これまでの大企業や行政への依存体質、住民が主体的に動かない体質を変えないと、地域は存続していけないと考えています。そのためにはゼロからイチを作る小さなプレーヤーがたくさん必要なんです。小さなプレーヤーが集まり、地域の中にコミュニティが醸成されることで、フルハウスのような個性的で多彩な事業が生まれてくると思います。これから先も災害が起こったり、環境の変化によって小さな事業が破綻してしまうようなことがあるかもしれませんが、そういう風土さえできていれば、次の世代が何か別のことにチャレンジ可能だと思います。そして、新陳代謝を繰り返しながら、50年、100年といったスパンで、町の機能が失われずに存続していく。そういう状態になることが最終的なゴールであると僕は考えます」

ベース=Baseとは、「基地」であり「土台」であり「基盤」であり「起点」である。この場所が、和田さんの目指すゴールのベースになることを願ってやまない
コミュニティの成立には衣食住だけにとどまらない、文化の場所も必要になってくる。その意味で、柳美里さんの活動に大きな期待を寄せている、と和田さんは言う。
「柳さんが小高で居を構え、活動してくださることは率直に言って嬉しいし、この地域がダイナミックに生まれ変わるためにはアートや文化は必須で、そういう要素を持ちこんでくれたことに感謝しています。事業として継続してもらわないと困るので、そこをNext Commons Lab南相馬や地域住民で、うまくサポートしていけたらと思っています」
文・榎本正樹