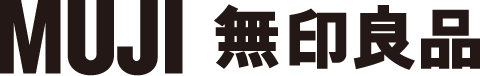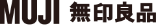裏通り。日々の風景をつくる人|かまがわ文庫
県庁所在地の駅から、例えば西にまっすぐに伸びる大通り。地元で生まれ育った百貨店のビルにはテナント閉店の張り紙。大通りから1本入った通りには、アーケード商店街。下校中の高校生の自転車の流れを縫うように買い物客が歩く。さらにもう1本、裏通りに入ると、シャッターを下ろした商店やコインパーキングが点在する中を点で繋ぐように個性的な古着屋さんや青果店や、小さなカフェがぽつりぽつりと。そのように外観される地方都市の町に個性があるとしたら、それはやはり、裏通りかもしれません。栃木県宇都宮市の中心部には、昭和23年に発足した全長約500mのアーケード商店街「オリオン通り」があります。その裏手を流れる小さく細い一級河川の釜川沿いの裏通りの一画に、2015年の4月、小さな「場」が新しく作られました。小さな黒板に、こんなメッセージが描かれて。
LEAVE A BOOK YOU’D LIKE TO SHARE
TAKE A BOOK YOU’D LIKE TO READ
裏通りに生まれた小さな文庫
ほかの誰かにも読んでもらいたい本を置いて。
あなたが読みたい本を持ち帰って。
誰もが使えるまちの本棚ができました。
誰もが使えるまちの本棚は、「かまがわ文庫」と名付けられました。手放してもいいと思う本を1冊もってきて、読みたい本を持ち帰る。こんなシンプルな仕組みの無人の文庫を始めたのは、小さな川を挟んだ向かい側でアパレルのセレクトショップcynic(シニック)を営む山田直由さんと公務員の坂井香林さん。
裏通りに面したオープンスペースに開かれた文庫は、次第に蔵書も増え、通りの商店主のみなさんや地域の方達、ときおり通りすがりの買い物客や昼休みにふらりと訪れる会社員など、さまざまな人が、本を媒介に行き交う場になっています。
「気に入った本があれば、持ち帰ってもらってかまわないんです。ここの本にはすべて、蕪のスタンプを押しています。いろんな地域に、小さな蕪(かまがわ文庫の略)のスタンプが押された本が広がるって、なんだか楽しいでしょ」
と、坂井さん。本を持ち帰って読んだ方が、「ありがとう、また来ます」の手紙を挟んで戻してくれることもあったと聞きます。

山田さんは、大学を中退してこの近辺のお店で働いたあと、19年前に独立して自分のお店を開きました。
「裏通りのこの一画には商店会があるわけではなく、気の合う8店舗が緩やかに繋がっています。オリオン通りに対して裏通り。その立地が好きで、ここに店を出す人がいて、ふらりと遊びにくる人がいる。お店を始めた頃と、この通りは、あまり変わっていないですね。相変わらず静かなまま、というか…」
と、笑顔を見せる山田さん。その状況を、そう悪いことだと思っているわけでもなさそうな表情です。
もうひとりの発起人、坂井さんは、宇都宮で生まれ育つも、若い頃は一度も足を踏み入れたことがなかったエリアだと言います。市の職員である坂井さんが中心市街地の担当になったのが5年前。その時に、釜川沿いに事務所を構えていたデザイナーに、このエリアで始めるイベントの相談を持ちかけられたのが最初の縁だったそうです。山田さんいわく「相変わらず…」というこの小さな裏通りにも、これまでには、いろんな動きがあったようです。
宇都宮市でも20年以上前から、行政が中心に、あるいは起点となって中心市街地の賑わいを取り戻していこう、というさまざまな試みが始まっていました。釜川エリアは、戦前までは水質もきれいで、川沿いの通りには染物屋や鰻屋もあったそうです。流域の開発が進んだ戦後は、水質の悪化や大雨時の氾濫を解消するための改修がなされ、釜川プロムナードと名付けられて、親水公園として緑化やベンチの設置などの整備が進められてきました。
昭和の時代の商店の建物の風情が残る水辺の通りには、洋服屋さんや雑貨店、ヘアサロン、飲食店など、個性的なお店が並びます。その一画で、山田さんが初めて他の店舗オーナーとプロジェクト的なことを行ったのは、2011年の震災直後の初夏のことでした。
山田:
「計画停電でお客さんも来ないし、いろいろ考えたり作ったりする時間があったんですよね。それで、うちと他のお店のオーナー達やデザイナーと相談してチャリティTシャツを作りました。売上は赤十字に寄付して、その後2回は続けたかな。それからですね、もっと多くの人に釜川沿いの魅力を楽しんでもらおう、なにかやろう、という流れになってきたのは。それで2012年に始めたのが、釜デパなんです」
釜デパ? KAMAGAWA DEPARTMENTのことですね。坂井さんが相談を受けたというイベントも、釜デパでしたか?
坂井:
「そうなんです。相談ごとは、イベント時に設営するテントを組むための竹のこと。必要な量だけ切らせてもらえる竹林を探している、という内容でした」
KAMAGAWA DEPARTMENT、通称「釜デパ」は、毎年8月第4土曜日に行う、商店主たちが発起人となり企画や運営からすべてこなした民間のイベントです。通り沿いに、自分たちで切り出した竹を用いて作ったテントを並べ、地元の商店だけでなく他の地域の人気店も呼び、まさに手づくりの1日限りの「釜川百貨店」とも言える催し。買うこと、食べることだけではなく、近隣の大学も参加し映像のパフォーマンスやキャンドルでの空間演出などもプログラムに組み入れられ、このエリアでいかに楽しい時間を過ごしてもらえるか、地域の商店主さんたちの気持ちが込められたイベントでした。
イベントの、その先の風景へ
かまデパが始まった翌年、2013年には、空き家をリノベーションしたシェアハウス「KAMAGAWA LIVING」や、「かまがわ文庫」が場を借りているオープンスペース「KAMAGAWA POCKET」が生まれています。そして、釜デパに参加する商店などが中心になって、毎月第4土曜日は営業時間を22時までに延長して夜の町歩きを楽しんでもらう企画、「かまがわよるさんぽ」も始まりました。
そして2015年の春、4回目の夏の「釜デパ」に向けて始動する時期に、実は山田さんは、イベントの目的や意味、続けることについて悩み始めていました。毎年回を重ねるごとに認知度もあがり、大勢のお客さんが楽しみにして1日限りのお祭りに集まるようになっていたのですが…。
山田「たしかに、街の中のハレのイベントにはなっていたと思います。でも、主催する僕たちが疲れ始めていた、というのが正直なところ。竹林に行って大量の竹を切り出すところから始めて、出店者を募って、調整して、打ち合わせして、発信して…それをそれぞれのお店の開店前や閉店後にこなしていくことが、次第に辛いものになってきて…。身の丈以上のことをして、自分たちが楽しめなくなっていました」。
「かまデパ」の閉じ方を意識し始めながら、山田さんが新しく形にしようとことは、子どもの頃から水のように空気のように、自分自身に吸収し続けてきた本に関するイベントでした。
山田:
「最初は、いまの『かまがわ文庫』のような常設のスタイルではなくて、1年に1回、本にまつわるイベントをここで開催できたらいいなあと考えていたんです」
山田さんが最初に相談したのが、かまがわポケットの代表、中村周さんでした。当時、市内の大学で建築意匠を学んでいた中村さんが、アトリエ兼住居として使える建物を探すなかで巡りあったのが、釜川沿いの築60年の空き家でした。地元の工務店さんにお世話になりながら大学の仲間や後輩とリノベーションを進め、どうせ住むなら、まちづくりの拠点としてみんなで使える場にしようと考えたそうです。道沿いにイベント用のオープンテラス、その奥にミーティングにも使えるアトリエ、そして住居スペースという3つのスペースをもった拠点が、2013年秋に、山田さんのお店の向かいに生まれていました。
相談を受けて山田さんのプランを聞いた中村さんは、「そういう企画は、坂井さん好きですよ。きっと一緒にやる!と賛同してくれますよ」と、かまデパを契機に繋がっていた坂井さんの名前を挙げました。「本にまつわるイベントを年に1度」という山田さんの話を聞いた坂井さんは、「年に1回の大きなイベントをやるより、小さなものでいいから毎月1回とか、定期的に開催したほうがいい、私もやりますから!」と山田さんに提案。坂井さんは「中村くんの予言通りになったわけです」と笑いながら、そう提案した理由を話してくれました。
坂井:
「かまデパを開催して通りが賑わったとしても、イベントの時だけのお客さんが多くて日常的な集客に結びついていないように見えていたんです。県内のいろんな有名な飲食のお店にも声をかけて出店してもらっていたので、お客さんの中には、そんな有名店を追ってイベントを渡り歩いて楽しむ人たちも少なからずいらっしゃいます。結局は、イベントの時だけのお客さんが増えて、経済の面でも人の繋がりの面でも、日々が、日常が、潤わないと意味がないんじゃないかなあと思っていて…。釜川エリアだけではないんですが地域振興のイベントって、そもそも何にためにやるんだろう?というモヤモヤした懐疑的な疑問をずっと持っていました」
そんなモヤモヤは、山田さんも抱えていたモヤモヤとも重なりました。1番最初の打ち合わせから、そもそも何のために? 無理なく続けていくには?と、意見交換を重ね、約2週間でコンセプトや仕組みなどを固め、ブログの開設まで進んだそうです。「本を通していろんなことを伝えたいと思っていた山田さん、拠点として作ったKAMAGAWA POCKETから街の風景を作りたいと思っていた中村くん、そして、いろんな地域振興やイベントを見聞きしていて、居場所作りの必要性を感じていた私。それぞれの思いが重なり合って、短期間でも中身の濃い組み立てができたと思います」と、坂井さんはその2週間を振り返ります。一致したビジョンは、小さな催しを「毎月1回」を続けていく先に、土地に根づく「場」が自然とできてくる…というイメージです。
山田:
「常設での無人の『かまがわ文庫』と、そのスペースを使った月に1度の催しを同時に始めました。両方を行うとことで、イベントのハレの空気も日常のものに変わっていく、いい流れができるのではないかな、と」。
2015年の5月に始まった月に一度の催しは『ツキイチトショカン』と名付けられ、この3月で23回目を終えました。参加者の方たちといい時間を重ねていることが、ウェブサイトのブログからも伺えます。毎回テーマを決めて、テーマに沿った本の展示を基本的にふたりの蔵書から行い、インスタレーション的な空間の作り込みがなされています。テーマによっては、ゲストを迎えて本のセレクトをお願いしたり、作品の展示をお願いすることも。基本的に毎月第3土曜日に開催し、17時に開場して21時に閉館。日常的に文庫を利用してくれている近所の方たちや、遠方からの固定ファンも。毎月口コミやネットで知って訪ねてきてくれる人も増えています。当日、飾り付けの準備などをしていると、ふらりと様子を見に来た通りの住人の人が手伝ってくれることもあるそうです。
かまがわ文庫の開館から1年と2ヶ月、オープンデッキに本が並ぶ景色が町の中に馴染んできた2016年の7月、かまデパのブログに「少し残念なお知らせを」として、休止のアナウンスがありました。「諸事情により今年はお休みすることにいたしました」「何もやらなくなるわけではありません。何か新しいこと考えてます。釜川らしいこと。釜川でしかできないこと。いろいろ決まったら、その時はお知らせします。今後とも釜川の端っこをよろしくお願いします!」と締めくくられていました。休止の理由には、主要メンバーの引越しや商売上の理由による引退などもありました。「地域のために大きなイベントをやるだけでは、地域の日常そのものが続かなくなっていた」と山田さんは振り返ります。年に1度のハレの日の賑わいから、日常の風景へ、バトンが渡された夏でした。

かまがわ文庫。朝の風景、夜の風景。
ツキイチトショカンの昨年12月の回のテーマは「ART」でした。ゲストに県内益子町在住の彫刻家、古川潤さんを迎え、会場全体を古川さんのアトリエのように仕立て直しました。このために、工具や道具を並べる棚も設え、古川さんの蔵書も展示し、来場の方たちに見てもらいました。山田さんと坂井さんの蔵書からも、単なる「アーティストの作品集」や「図録」ではなく、おふたりの言葉で言うと「アートと呼ばれるものが生み出される過程、環境、思考などが感じとれる本」も並びました。

写真右端がこの回のゲスト、彫刻家の古川潤さん。隣が山田さん。近所の常連さんも訪れ、それぞれが気になる写真や本を手に、あれこれ語り合いながらページをめくっていく。

空間構成は、山田さんが、ルーマニアの彫刻家ブランクーシのアトリエをイメージして古川さんに相談。道具や素材などを実際のアトリエのようにディスプレイした。
今年の2月は『かまがわ文庫』の拡大版として「文庫」をテーマに開催。冒頭で紹介した英文の文庫のキャッチコピーが入ったバッグも、シリアルアンバー入りで限定販売したそうですが、その仕組みが楽しさに溢れています。壁に展示されたバッグには、シリアルナンバーが表示され、自分が好きな番号や、手刷りゆえに微妙に1つ1つが違う印刷の様子から好きなものを選んで壁から降ろしてもらうと、シリアルナンバーが書かれた紙が現れます。そこに記念に名前をサインしてもらい、バッグの中には、1冊の文庫本が入っています。番号の選び方や、サインの様子、中に入っていた文庫本について…参加者の方たちの感想や感性やツッコミが飛び交い、おおいに盛り上がったそうです。まさに、日常に用意する環境と定期的に行う手作りの催しが、リンクしながらコミュニティの場が作られているように思えます。
テーマ設定や空間作りのアイディアは、毎回すんなり決まるのでしょうか?
山田:
「テーマは、まずざっくりと決めて、それからふたりで丁寧に意見交換を続けて、方向性を絞り込んでいますね。デザインがテーマを決めたら、そこからもっと絞り込む過程を大切にしています。グラフィックだけにするのか、工業デザインも入れるのか、入れるとしたらどんな切り口で?とかね。広げるのはいくらでも広げられるけど、絞り込む過程って大切だと思うんです」
坂井:
「どちらかのアイディアですんなり決める、ということはしないですね。ふたりで、あーだこーだと意見を交わしながら、歩み寄れたところで落とし込んでいく、あ、これだね、ということが見つかるまで話します」
山田:
「3月までに23回やってきて、同じテーマで趣向を変えてやったこともありますが、10年は続けたいと思ってるんですよね」
坂井:
「とにかく続けないと意味がないし、その先も見えてこないですからね」
山田:
「必要とされ続けることが大切だと思ってます。いくら楽しそうなことを仕掛けても、人が来ないと意味がないし…」
空間の作り込みも、毎回凝っていますね。
坂井:
「どうやったら楽しんでもらえるか、そのテーマの世界に入ってきてもらえるか、そこを考えますね」
山田:
「ある程度は、かっこつけることも大切だと思います。この空間に一歩入ったら、わーっ!とか、おっ!とか、新鮮な驚きを持ってもらえたら嬉しくて…」
坂井:
「そうなんですよね。なおかつ、本から離れないようにも気をつけています。冬の本をテーマにした時は、たくさんの紙風船で雪を表現したり、怖い本がテーマの時は、黒い蝶を大量に吊るしたり貼ったり。余っていたコピー用紙を墨汁で染めて乾いたら切って、900羽の蝶を作りました。どう置いたら怖さを感じてもらえるか…、来てくれる人の反応を思い浮かべながら作業していました」
山田:
空間の構成と、展示して見てもらう本とで、ちょっとした驚きだったり、新鮮な難道だったり、気負いなく、ちょっとした刺激を、来る人に与えられる場所にしていきたいですね」
坂井:
「それから、何か1つでも行動に繋がるといいなと思います。植物をテーマにした展示だったら、明日、種を買いに行こうと思ってもらえるとか…」
ふたりで毎回の作り込みと準備をするのは大変ですね?
坂井:
「いろんな人を巻き込んでいますから。ゲストとしてお願いする方も近所の人もみんなでつくる空間です」
山田:
「この場所の住人も、中村くんの就職にともない、いまは後輩の学生、二瓶賢人くんに代わっていますが、もちろん彼も用務員補佐としてサポートしてくれています」
用務員補佐ですか?
山田:
「坂井さんが館長で、僕が用務員。補佐が二瓶くんの他にも何名かいて、秘書役や監査役もいます。何か肩書きが欲しいという常連さんもいて、謎の肩書きもありますが、巻き込んだ人、巻き込まれた人で楽しみながらやっています」

ツキイチトショカンの夜は、本を手に語り合う輪ができる。写真左の右端から用務員補佐の二瓶さん、館長の坂井さん、KAMAGAWA POCKET代表で、かまがわ文庫監査役でもある中村周さん、お客さん。
受け身では楽しめない「本」がある企画だからこそ。
最後に、山田さんに「なぜ、本だったのか?」という問いを投げかけてみました。あたりまえの自然なことのように「本のイベントを考えていた」と語る山田さんに、最後まで聞きそびれていたのです。
山田:
「子供の頃に読んだ、さとうさとるの本を今でも大切にもっています。とにかく本を読むことも、本を手にすることも、本にまつわることがずっと好きでした。いまは、アパレル中心のセレクトショップを営んでますけど、物心ついた頃から今までに読んできた本や手にしてきた本を自分の中にインプットしてきて、それから僕自身の中で蓄積したり身になったりして、アウトプットしたものが、このショップとも言えると思っています。だから、僕が本を扱うことは、この店の背景を伝えることにもなるんじゃないか、つまり、どんな背景をもった、どんな人が、どういう考えで開いているお店なのかを伝えることになるんじゃないか、と。洋服屋のアプローチとして本を使うのは、面白いと思ったんですよね。それで、店の中には大きな本棚に蔵書を並べていますし、2014年ごろからは、僕が読んだ本も店頭で売り始めたんです。お客さんから、オススメの本を教えて、と話しかけられるようになったり、これを読んだことがあるんだったら、次はこれなんかどう?と、会話も自然と生まれるようになったんですよね。今の所は、ショップの戦略としてはそんなにうまくいっていないかも…(笑)。でも、本を入り口にして店に来てくれるようになった人も少しいます。
本を入り口にするというのは、実は誰にでもわかりやすいものではなく、ある意味で割り切ったアプローチだとも思います。読書って、受け身じゃできない、自分で本を開かないといけない能動的な行為ですよね。自分で開いて自分で読まないと、その世界に入っていけない。そういう行動を起こせるかどうか、与えられたことに行動を起こせるか、そのエネルギーがあるか、ハードルであり線引きだと思うんです。でも、文庫とトショカンをやってみて、話が合う人や、この通りで何をどう見ていくか、方向性が同じような人の繋がりが広がりました。文庫をベースにした活動を、繋がった仲間たちと楽しみながら続けていける手応えも感じています」

3月11日には、KAMAGAWA POCKETの中村周さんが企画発起人となり「釜川から育む、まちのビジョン」と題したシンポジウムが宇都宮市内で開催された。釜川エリアのこれからを考えよう、という呼びかけにパネリストとして坂井さんは参加しました。「イベントを開催する際に、店が潤うようにコーディネーターが入って議論を活性化させては?」「空地や空家をどう活かすか?」などの議論がなされたシンポジウムのあとで、坂井さんは、ブレることなく、こんなことを語ってくれました。
坂井:
「大切なことは、淡々と続けていくことだと思います。並ぶ本や訪れる人はいつも同じではなくて、でもだからこそそれが街の風景になると思うし、それに呼応するようにツキイチトショカンやかまがわ文庫も変わっていけたらいいと思います。川のように、いつもと同じに見えるけど違うものが流れているみたいに、です」
そこに住む人の、それまで歩んできた日々の延長上にある小さな「思い」から始まること。それが周囲の人の潜在的なニーズと重なって共感の輪が広がっていくとき、日常の風景のひとつとして町に根づいていくものとなるのでしょう。背伸びすることもなく、一時的な助成に頼ることもなく、「ふたりの蔵書」を出発点にした、人が集う場所。小さな裏通りの日常の風景から、大切なことが見えてきます。
写真・文:簑田理香
リンク:
かまがわ文庫
KAMAGAWA POCKET