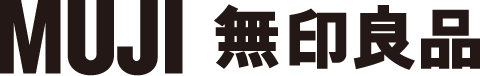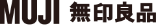神々が住まう山との暮らし
周囲の山々は木々の根本から雪解けがはじまり、長かった冬の装いを解こうとしている。モノクロームの世界に、いのちを孕んだ鮮やかな色が戻って来るのももうすぐだ。
深い雪に閉ざされていた世界からの解放は、雪の国に暮らす者にとっては心浮き立つ季節だ。しかし一方で、極めて危険な時期でもある。
年間平均降雪量が約7メートルという奥会津では、この時期の雪解け水の量もまた膨大なものとなる。雪の下に隠れた小川からはゴーゴーという水の轟く音が響き、杉の小枝でふさがれた川から溢れた水は、各所に湖のような水たまりを作る。この雪解け水が土砂崩れを誘発すると、家屋が流されたり、倒木が停電や道路封鎖を引き起こすことになる。
「美しい自然」と愛でてきたはずの自然環境は、その言葉と裏腹に、放置されたまま荒廃を深める危険な山林となってしまった。
適切に管理された健全な森林とはどんな姿をしていたのか。その記憶さえあいまいになって久しい。森林面積が県土の約7割を占めるという福島県は、今、その本来的なはたらきを失いつつある。
放棄された里山
かつては「春木山」という、早春の山から柴を刈る営みがあった。炊事や暖房用の燃料として不可欠の作業で、秋までに完了する一冬分の薪の確保もまた、不可欠だった。燃料を調達するだけでも、里山は十分に管理された状態だった。陽が差す明るい広葉樹の疎林の下は腐葉土が堆積したふかふかの地面で、多様な植物に彩られた山菜の宝庫でもあった。薪炭林として機能していた里山は、子供も自在に遊ぶことの出来る安全な学びの領域だった。
昭和30年代の国の林業政策によって、畑地のみならず、標高の高い奥山まで伐り開きスギを植栽してきたが、価値を失ったスギ林もまた、放置されたままだ。会津は急峻な傾斜地にスギが植林されているところが多い。
思惑が外れた林業政策と地下資源にゆだねた消費社会の拡大という、林業にとっては二重の打撃によって、里山と奥山は境界を失ったまま荒廃の一途をたどっている。人家の周囲や田畑のほとりまで、鬱蒼と暗く危険な奥山が迫っている配置だ。手入れされないまま伐期を迎えたスギ林では大量の花粉が舞う。活用資源としての間伐、除伐が為されないために木が込み入って、雨が降ると表土が流されて一箇所に集中するため、土砂崩れが頻繁に起こっている。メダカは姿を消し、チョウの種類も激減した。蛍が生息する場所も年々減っている。
薪炭林がスギやカラマツなどの針葉樹林へと転換したことで、里山は、保水力を失い、小川は水量が減少して汚れている。多様な野生動物は、こうした棲息環境の激変に対応できずに里に下りてきている。里山は野生動物との棲み分けを明確にする境界でもあったが、その緩衝帯がなくなったことは、動物たちにとっても人間にとっても悲惨なことだ。
さらに、平成12年頃から県内に広がり始めたカシノナガキクイムシによる広葉樹の被害は、ピークを過ぎたとはいえ想像以上の速度で拡大している。ナラやクヌギなどの老木に寄生するといわれる害虫だが、込み入った樹木間では食い止める手立てもなく、全山を覆うように立ち枯れた山は、もう、二酸化炭素を吸収することはできない。他の樹木に遷移するまで手をこまねいて待つしかないのが現実である。
そして、原発災害が起きた。
被害が軽微だった会津の山林は、かろうじて残された貴重な自然資源である。これ以上の荒廃を食い止め、保全の取り組みがなされなくてはならない。

神々との暮らし
山に依拠する会津の農の暮らしは、御し難い自然への敬虔な姿勢から豊かな精神文化も育んできた。とりわけ奥会津地域では、節ごとの多彩な年中行事は今も続けられている。
見えざる神々が座すところ、他の生き物が棲むところ、人間が恵みを頂くところ。棲み分けは暗黙のうちに決められていた。
鬱蒼とした暗い奥山に入ることのできる人間は、熟練の林業家や猟師、山菜採り名人などに限られており、そうした人々は危険と隣り合わせの生業ゆえに山の恐ろしさも熟知している。山での不文律を堅持し、作業の安全を祈願することは、みだりに踏み込んではならない場所や、人間以外のいのちに対する礼を尽くすための儀式でもある。
正月の二日に行われることの多い「山入り」という行事は、一年間の山での仕事の無事と豊かな恵みを願って行われている。縄を綯って輪にしたケンレイには、御幣とスルメや昆布、餅が挟まれていて、これを雪深い山の入り口の木の枝に捧げる。この儀式が終わらないと、刃物を使ってはならないとされた。帰り道、アキの方角(その年の恵方)から若木を2,3本伐って持ち帰り、雪の庭に挿しておいて春からの畑作業の垣柴にする。
さらに、小正月の1月14日、伐採のための道具から包丁に至るまで、日ごろ使用する刃物を並べて供物を捧げ、道具にも人間と同じように歳取りをしてもらう「道具の歳取り」という行事がある。
この慣わしを続ける人も年々少なくなってきているが、私たちは自然の豊かさだけを享受することはできない。いつ牙をむくかも知れない災厄が、常に裏側に張りついているのは今も変わらない現実である。恵みと災厄の両極を見せる自然は、その強大な力ゆえに見えざる神となる。自然の呼吸と向き合うとき、人は身を低めて畏れ、敬うしかなかった。それが、自然を傷つけることでしか生きられない人間の、自然との均衡をかろうじて保つ姿勢だった。
里山の荒廃は、見えざる神の存在も、災厄への畏れも忘れさせたのかもしれない。
しかし、荒れ続ける山々は、いつか必ず災厄をもたらす。大震災と津波と原発災害とを経験した私たちは、再び山への畏れを取り戻さねばならない。
自然のめぐりの中にちりばめられた神々との物語を、これからいくつか紹介していきたいと思う。
文:奥会津書房 遠藤 由美子