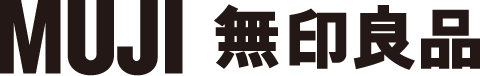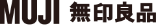東京で採り、つくり、使うプロダクト「Ao.」から。-これからのものづくりのあり方を探る-
建築・都市などのメディアを手がける編集者・ライター。大学院にて国土計画を研究したのち、建築専門の編集プロダクションに勤務。2019年独立。合同会社オフセット共同主宰。
多くの人がもつ “地元” 。ひとくちに地元と言ってもさまざまですが、多くは、飾り気がなく退屈だけど、どこか安心感があって気にかけてしまう場所ではないでしょうか。また、きらびやかな都会のイメージをもたれる東京も、誰かの地元であり、退屈さと安心感を感じている人たちが実はたくさんいるのです。そんな東京で生まれ育ったひとりの建築家と東京を拠点にする家具職人がつくる東京ローカルなデザインプロジェクト「Ao.」。「Ao.」ができるまでのストーリーを通して、プロダクトと地域の関係性を紐解いていきます。
「リノベーション」に見出した、新しいものづくりの可能性
建築家の宮地洋さんは、1986年、東京都立川生まれ。小さい頃からものづくりが好きだったことや、美術家をしているお姉さんの影響もあって、大学で建築の道を選択します。建築設計を学ぶなかで設計の面白さと同時に、違和感を抱いていったと言います。
宮地さん:
「今から振り返ると、僕が大学生だったころの設計課題では、建物をつくることによる周辺社会への責任や自然環境への配慮などについてはあまり議論されていませんでした。そのような設計の授業では学べない部分への興味がだんだんと膨らんでいきました」
その後、宮地さんは大学院へ進学して都市計画の研究室に所属しながら、学外で日本橋のビル《Creative hub 131》のリノベーションプロジェクトに関わることになります。これは、古いビルをアーティストの新野圭二郎さんが1棟借り上げて、コワーキングスペースや食堂などのオルタナティブスペースにつくり変えるプロジェクト。縁があって、宮地さんはこのプロジェクトの初期から関わり、設計、施工、運営に携わりながら場づくりの可能性を感じたそうです。
宮地さん:
「《Creative hub 131》の経験を通して、新築ではなく既にあるいい空間を見つけ出し、それをより良くすることのほうが僕にとって価値のある空間づくりだという実感を得たんですよね。それから、リノベーションで理想の空間をつくることが自分にはあっていると思い、そうした道へ進んでいきます」
大学院卒業後、宮地さんは建築家の吉村靖孝氏が主宰する建築設計事務所に務めます。吉村氏は、コンテナを使った建築のプロトタイプやモバイルハウスを提案するなど、建築をつくる仕組みやプロセスの設計に取り組む建築家です。そこでさまざまな「場」をつくる仕組みを実践を通して学び、2015年に独立。「anova design/アノバデザイン」を立ち上げます。
「anova design/アノバデザイン」とは、「あの場をつくる」と「場のイノベーション(Inovation)を起こす」という意味をもった名前。独立後、宮地さんは日本橋を拠点に、建築・空間の企画・設計・運営・管理まで幅広い活動を行い、新しい場づくりに取り組んでいます。
こうした既存の建物の可能性を活かすリノベーションや、建築を仕組みから考える取り組みを経て、地産地消でサスティナブルなプロジェクトである「Ao.」が生まれました。
多摩の木材×大田区の工房
「Ao.」は、東京の無垢木材を藍染めしたデザインプロダクト。現在(2020年4月時点)は、ヒノキでできたテーブルとイス、サクラでできた皿とボードがラインナップされています。プロジェクトとしての「Ao.」を立ち上げたきっかけについて、宮地さんはこう話します。
宮地さん:
「僕の兄は東京で林業をしているのですが、その兄から東京の山々にも樹齢100年を超える良木がたくさんあると聞いていました。でも、そうした東京の良木多くが、用途がなかったり、製材のコストを考慮して伐採後すぐに他の間伐材とともにウッドチップや産業廃棄物にされているそうなんです。だから、新しいプロダクトをつくることで、流通経路を開拓し、そうした東京の資源を有効活用したいと思い、メイド・イン・トーキョーのプロダクトをつくることができないかと考えました」
プロジェクトの始まりは、Ao.の共同者であり木工職人の田中良典さんとの一つの家具づくりでした。宮地さんと田中さんは学生時代、香港・マカオで行われた建築ワークショップで出会った間柄でした。当時、建築学生だった田中さんは、大学卒業後に家具職人になる道を選び、飛騨高山の木工専門学校、岡山県西粟倉村の家具工房を経て、2016年に家具職人として独立しました。ワークショップ後はたまに連絡を取り合う仲だった二人ですが、大田区蒲田で再会を果たします。

工房で打ち合わせをする宮地さん(右)と田中さん(左)
宮地さん:
「田中さんが独立して東京で木工のできる工房を探していました。ちょうどその頃、僕は大田区蒲田のシェアスペース『カマタ_ブリッヂ』でデジタルファブリケーションを用いて什器を制作していました。スペースを運営する@カマタは蒲田周辺のエリアマネジメントをしていたこともあり、田中さんに2階に空きのある町工場を紹介することができました。田中さんはそこを借りてfurniture studio KOKKOKとして家具づくりの活動を始めました。そういうふうに、期せずして僕ら二人の活動拠点が重なっていったんですね」

東京都大田区蒲田の町工場でAo.がつくられている
田中さんの独立後、たびたび家具製作の仕事を依頼していた宮地さん。そんななか、2年前に日本橋にあるベンチャーオフィスに入れるテーブルを製作するときに、東京産の無垢の木材を使った家具をつくりたいと田中さんに持ちかけました。そこでまず、兄に材料の相談をし、兄の貯木場に置いてあった厚さ7cmの無垢の欅の板を4枚譲り受け、それらをつなぎ合わせた1枚の天板を制作します。
また、「Ao.」のもうひとつの特徴である藍染のアイデアは、天板を青に染めたいという宮地さんのイメージと、木材の草木染を試作していた田中さんのノウハウによって生まれたものでした。こうして最初の藍染のプロダクトが完成します。
これを出発点にして、「Ao.」の製品化が進められていきます。

藍染されたAo.のプロダクト(写真:NOJYO高木俊幸写真事務所)
プロダクトであり、物語でもある「Ao.」
「Ao.」をプロダクトとして成立させるために、3つの課題がありました。
ひとつは、無垢の家具を藍染することの難しさ。「Ao.」のプロダクトは様々な樹種を活用するために、異なる木材の色を藍色に統一し、強い個性を生み出しています。しかし家具として使用するには染めムラや色移りを無くす染色方法の開発が必要でした。布を染める方法ではうまくいかず、木材を藍染するために試行錯誤を繰り返して独自の技法を確立していきました。
ふたつめは材料の入手経路の開拓です。木材は、伐採した木を木材として使えるようにするまでには、製材・乾燥という工程を踏みます。伐採後、山から木を下ろし、板状に製材してから、家具として使える材料とするために乾燥(自然乾燥の場合は数年間必要)を行うので、それを担ってくれる人と場所が必要でした。そのために二人で多摩の製材所を探し、あきる野市の沖倉製材所さんに協力してもらえることになりました。
そして最後が商品の販売です。二人それぞれが受注する家具やインテリアの仕事だけで納入していくことも可能ですが、商品として自立させ、東京産の木材が広くたくさんの人のもとに届いてほしいと考えていました。そのため、「Ao.」のロゴデザインやウェブ制作、プロダクトの展示会「DESIGNART TOKYO 2019」への出展などを通して、「Ao.」を販売する仕組みづくりを自分たちで行っていきました。
この「Ao.」がメイド・イン・トーキョーのプロダクトとして、世界に広まってほしいと思う一方、東京にいる人にこそ使ってほしいと宮地さんは話します。

沖倉製作所で乾燥されてる木材
宮地さん:
「今のデザインに求められている大きなテーマは、 “人の生活を豊かにするものであり、同時に自然環境を守ることに通じる” と考えています。また、自然環境への配慮は生活のなかにある家具や内装にも意識されるべきことだと思っています。東京の多摩で伐った木を使い、東京の大田区でつくられた『Ao.』の制作背景を知ってもらえることで、”地元”の自然環境への意識を感じることのできる地産地消のプロダクトになって欲しいです。そしてそれは、東京で使われることでより意味を増していく。だから、東京の人にこそ使ってもらいたいです」

Ao.の椅子と机(写真:NOJYO高木俊幸写真事務所)
「Ao.」はプロダクトであり、つくられ方が刻まれた物語でもあるのかもしれません。そして、自然環境への配慮の大切さを日々忘れないために、標語を貼っておくのでなく、「Ao.」を日常に置いておく。そんなことが宮地さんの考えている、これからの “デザインのあり方” のようです。宮地さんはさらにこう続けます。
宮地さん:
「僕がリノベーションを前提とした場づくりをしている理由は、資源を大事にするという側面もありますが、既存の建築には既にたくさんの意味や文脈が介在しているからなんです。意味や文脈があると、そこに愛情やリスペクトが生まれてくる。そうした感情なしには、空間もプロダクトも次々とスクラップされていくだけだと思うんです。僕は自分の仕事を通して、いろんな人たちと一緒に、その場所や物の価値を探し出し、つくり出すことをしたいと考えています」
ローカルで消費するものを、ローカルにつくることが当たり前の世界へ
宮地さん:
「『Ao.』って、プロダクトでもある一方で、仕組みでもあるんですよね。その地のものを使って、その地の職人が、その地で使うものをつくるという仕組みです。プロダクトとしての『Ao.』は東京ローカルなものですが、この仕組みを日本各地、世界各国で展開できたらいいなと思っています。僕自身、この仕組みをもって各地の人たちとコラボレーションをしてみたい。その結果として、この地域では家具だったけど、この地域では小説ができた、なんてことができたら面白いですよね。そうやって、ローカルにおける消費と生産がローカルで成り立つことが当たり前の世界になるといいなと思います」
インタビューを通して、宮地さんから強烈なエネルギーを受け取りました。このエネルギーはどこから生まれるのだろうか?最後にそのエネルギーの源について聞いてみます。
宮地さん:
「まわりからは手間をかけてるように見られるのですが、僕は手間のかからない方法を選んでると思っているんですよね(笑)。たとえばホームセンターで売っているベニア材ひとつとっても、遠い国で木を伐採して、船で運んで、乾燥して、桂剥きにして、接着して、規格寸法に整えて、輸送して店頭に並びます。一方で僕らのやり方だと、間に入っている人の数って何百倍も少ないと思います。計算したわけではないですが、たぶん環境への負荷も僕らのやり方のほうが何百倍も少ないはずです。
それなのに手間がかかって見えるのは ”発見” で、そのぶん付加価値を感じてもらいやすいし、大事に扱ってもらえる仕組みになっていると思います。この仕組みは今後うまく活かしていきたいと思っています。そして、人に理解してもらえる場やプロダクトを、これからもつくっていきたいです」
最後に。この取材は3月末に行われたものです。その後、緊急事態宣言が発令され、日本国内ではさまざまな形でこの影響が現れており、宮地さんの計画していた「Ao.」を内装の一部に取り入れた新たなスペースも中止を余儀なくされました。
“人と会うこと” がハードルになってしまったポストコロナにおいて、公共的な空間のあり方は否応なく変わらざるを得ない状況に来ています。そんな、〈人〉と〈人〉とが出会うことが難しい社会では、〈人〉と〈もの〉が出会うことの設計が重要になり、「Ao.」のような物語を携えたプロダクトがより一層価値をもつのかもしれません。
文:山道雄太
写真:NOJYO高木俊幸写真事務所、山道雄太
リンク:
Ao.ウェブサイト
Ao. Instagram