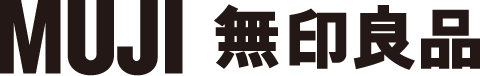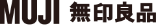自然に委ねるアートの話 −桜島・火山灰、奄美大島・泥染−
料理教室チャノマ主宰。白崎裕子に師事、アシスタント、白崎茶会講師を経て独立。鹿児島県鹿児島市在住。地粉を使ったパンや麺、お菓子の料理教室を開催。
鹿児島のシンボルといえば、桜島。
その誕生は2万6千年前と言われており、現在も毎日のように小規模な噴火を繰り返しています。そこに暮らす人々は、農産物や温泉等火山の恩恵を受けながらも、暮らしに‘灰’がもたらす影響も大きく、日々風向きや降灰予報を気にかけ、火山とともに暮らしています。
鹿児島県鹿児島市は、高台や斜面に住宅地が多く、噴煙を高くあげる桜島の姿を、多方面から見ることができると同時に、‘灰’の影響を受けるエリアの一つです。そんな場所に9年前に移住し、県民からは邪魔者扱いされてしまう‘灰’を見事なアートとして作品を生み出してきた美術家の北一浩さん。この地に暮らす中で生まれた作品について、その誕生や背景、魅力を伺いました。
生き方を考えて動いた先に、出会ったもの
北一浩さんは、大学卒業後、東京でグラフィックデザイナーとして広告代理店に勤務。その後、2010年~美術大学で助手を勤めながら、美術家として自身の作品を作るようになります。デザインを仕事にしながらアートをやりたいと思っていた頃、2011年の東日本大震災が起きました。同じころ、結婚して家庭を持ち、当時勤めていた大学の任期も近づき、子供を授かったタイミングも重なって生き方を考えるようになったそうです。西日本に限定して勤務先を探した結果、たまたま決まった先が鹿児島の地でした。こうして2012年4月より、鹿児島県立短期大学で教鞭をとるようになりました。
北さん:
「小さい頃に家族旅行で来て、桜島に行ったなくらいの記憶しかなかったのですが、引越して桜島の噴煙を間近で見て、おおっこれか、と思いました。丁度火山灰でなにか作りたいなと思っていた頃、『大桜島公募展』があったのでやってみようかなと思って。一番桜島らしい作品ってなんだろうと思った時に、桜島自体を使えばいいのだと思い、灰自体を画材にしました」

鹿児島移住後、最初に制作した「灰の絵」(2012年入選作品)
キャンバスに、桜島の火山灰に樹脂を混ぜたものを画材として描いた作品を作りました。公募展の入選を経て、手応えを感じた北さんは、現在も降り注ぐ火山灰に加え、太古から降り積もったシラス(姶良カルデラを噴出源とする堆積物、鹿児島県本土の半分を占めるのがシラス大地)を使って制作をはじめます。現在と過去の対比、黒と白のコントラスト、そのままの自然な色で表現された作品は、あるようでなかった‘異質’な作品となり注目を浴びます。日常生活に影響を及ぼし、邪魔者扱いされてしまう灰を見事に作品にしたことから評判を呼び、個展やワークショップを開催するようになります。

「灰の絵」展示会の様子(2015年)
泥染の布
北さん:
「しばらく灰の作品を作っていたのですが、鹿児島県の大島紬の活性化事業において、何かできないかという依頼があって。大島紬の職人さんや紬に限らず、奄美大島でデザインや物づくりをしている同年代の若い方を集め、パネルディスカッションを開催することになったんです」
その縁がきっかけで奄美に関わる作家さんの活動に興味を持ち、2016年日本クラフトデザイン協会と合同で「奄やどり」という展示会の企画を立ち上げます。北さんは企画兼副実行員長として舵をきりながら、作家としても自身の作品を手掛けることになりました。
北さん:
「大島紬の製造工程の中で “染め” の過程が一番面白いと思ったんです。染料自体も島に自生している車輪梅(方言でテーチ木)を使って、さらに鉄分の多い泥田につけて、すごく理にかなっていると思いました。泥染め自体は平安時代から続いているものらしく、せっかく美術館でできる展示なので、とにかく大きい泥染の作品を作ってみたくて。絵画用の大きなロールキャンバス(2m×10m)をリュックに丸めてつめ、奄美に持っていきました。広げて浸けるわけにもいかず、丸めたままの布を泥田に1ヶ月放置してみることにしたんです」
一般的には、テーチ木染めと泥染めを交互に何度も繰り返すことで、タンニン酸と鉄分の反応で赤茶色からだんだんと黒く染め上げますが、北さんは布を泥田に浸けたまま、1ヶ月後に引き上げるという独自の方法で泥染めを行います。そのサイクルと自然が生み出す美に感銘した北さんは、その作品をきっかけにその後も度々奄美を訪れ、“泥染の布” の制作に取り組むことになります。

テーチ木に一晩つけた布→泥田に浸ける→1ヶ月後、シマの海や川で泥を落とす
美術家というと、彫刻や絵画など専門分野において美術活動をされているイメージがありますが、北さんは特定の手段や分野を選ばないようです。制作意欲をかき立てられるものとは何なのか、現在主に取り組んでいる奄美大島での“泥染め“からさらに探ってみました。
伝統工芸の枠を超えて
北さんにとって奄美大島における作家活動に欠かせない存在なのが、金井工芸・金井志人さん。前述の「奄やどり」の実行委員かつ出品作家さんでもあり、金井さんが働く金井工芸は奄美大島で数少なくなった染色工房の一つで、本場大島紬の糸や絣をはじめ、様々なニーズに対応した天然染色を行っています。山でテーチ木を採取するところから始まり、煮出して染料を作り染色します。伝統技法である泥染めを共通に、ご自身でも染色家として様々な作品を作られています。
高校卒業後上京し、学生の頃から音楽や音響の仕事をしていたという金井さん。大島紬や泥染めをどうにかしたいというわけでも後継のためでもなく、地元で今後のことを考えようとUターンしたそう。家業について、先が長くないかもしれないという現実を目の当たりにし、幼少期から見てきた光景がなくなる前に、ちょっとかじってみようと思ったのがきっかけだそうです。
金井さん:
「色を作る工程がすごく面白く感じられたんです。普通は、画材屋さんで染料を買ってくるところを、まず色を山に入ってとってきて煮出してという様々な工程が、錬金術のようで不思議に思いました。子供の頃から見ていたはずなのに歴史や文化が折り重なってこういった工程ができたことに初めて気づいて、面白い!と思って。違う分野にいたからこそ、俯瞰的に見るようになったのかもしれません」
観光の方など一般の体験はもちろん、北さんのように魅了されて訪れる作家は、後を絶たないと言います。伝統技法である泥染めを惜しみなく分け隔てもなく公開し、ご自身も新しい技法や染めを探究している理由はなぜでしょう。

泥を落とした布 干して完成(2019年)
金井さん:
「金井工芸は、元々父が創業して約40年、染色工房は大島紬の分担業として担っていました。異業種を受け入れる業界ではなかったけれど、父の代からインテリアやアパレルからも依頼を受けています。材料は奄美にある自然を使うわけで、使いたいという人が使える状況にある方が面白いし、泥染めも知恵としてそこにあるだけで、全て僕らのものではない。使いたいという人に平等に機会があった方が、ごく自然なことだと思うんです。“伝統工芸” という人が作ったルールや括りよりも、泥染めができるのはこの ”自然” があるからという方が大きいと思っています。
北さんの構想を聞いた時、面白いと思ったし手伝いたいと思いました。泥田に1ヶ月つける人もいないし、単純にどうなるのだろうという興味の方が大きかった。やったことないことに興味が湧きましたね。北さんを始め、いろんな方がこの地を訪れ、染めの可能性を引き立たせてもらっていて、それによって見えてくるものが結構あるんです。奄美の文化があるからこそ生まれるというものは、伝統工芸だけではなくて、違う手法で認知されていくのも可能性としてあるなと」
伝統工芸というと先祖代々とか一子相伝のような堅いイメージがありますが、金井さんの答え自体があまりに“自然”で、それでいて新しいことや可能性を受け入れて愉しんでいることに驚きました。そして“自然”は皆に平等にあるものであり“泥染め”の知恵も僕らのものではないという概念に、“自然あってこその私たちの暮らし”という根本においても、諭されたような気がしました。
‘シマ’がつくる色
出る色を狙って染める場合もあるという金井さんですが、北さんは全くの逆だと言います。

金井工芸にて 金井さん(左)と北さん(右)
北さん:
「僕は染色をしている感覚があまりなくて、興味があって面白いなと思うことが、側から見ると染色。次これを染めたいとか、これを染めてみたいというよりも、自分の琴線に触れるような単純に響いたものが出た時にやらせてもらうという感じなのかな。シマのテーチ木で染料をとって、シマの土で染めるというサイクルが、1000年以上続いているって物凄いことだなと」
北さん:
「自分でコントロールができないんです。同じようにやっても毎回色味も違うし、泥田自体に1ヶ月おくから自分はその場にいないし、天気、時期や泥田の状態、台風が来るこないによっても毎回違う。美術・芸術=美しいものと考えた時に、作らなくても美しいものはそこらへんにいっぱいあるし、結局自然には勝てないじゃないですか。僕が作る行為自体が違うんじゃないかと、これをやっているうちに思えてきて。なるべく自分の作家の恣意性を排除しています」
金井さん:
「最近は気候の変化を感じます。雨が降る時はものすごく降るが、降らない時は全く降らない。泥田が枯渇するんじゃないかって思います。地下水で戻してあげたりもしますが、自然な形ではないなと。採れる植物も、色の出方も若干変わっているような気がしています。去年イギリスでワークショップをした際に、環境の変化にどう対応していくか?と問いが多かったんです。テーチ木と泥で泥染めですという工芸的に決められた定義があるとしても、もともとは自然に合わせるのが仕事。違うもので泥染めして対応していくしかないだろうし、持続可能ではないので。次やるならこれだろうという植物も実はあるんですよ」
先人達も、きっと昔から自然の変化に合わせてきたと思うし、これからも柔軟に対応して島の恵みに感謝して染色を持続していきたいと話す金井さん。作風は違えど、自然を原料に自然に委ね、作品に取り組む北さんと同じ志を感じました。
工程こそ自然の美
北さん:
「自然が作る美であって、自分が作っていない事が、すごくいいなと思っているんです。灰自体もそうですね。地震や災害を目の当たりにして、知らず知らずのうちに自分の感覚になってきたのかもしれない。どういうものができようとできたものが全て。いいとか悪いとかなくて、工程の方が大切で、だから飽きずにできているのかもしれません。極端な話、僕でなくても作業自体は誰でもできる。泥染めに関しては、シマが作っているんですよね。自然には勝てないという思いは移住のきっかけでもあるし、作品を作る上でも自分はサポートするだけ、今後もその観点は大事にしたいと思っています」
1ヶ月置きっぱなしの状態は心苦しいが、伝統工芸から飛び出して色々なことをされている金井さんだからこそ、広く理解があると思う。世界でここしかやらせてくれないだろうなと笑う北さん。この夏も大きなキャンバス生地をリュックに詰めて、奄美へ行きます、と夏休みを心待ちにしている少年のような満面の笑みで話してくださいました。
あくまで自然に沿って自然体で自然美を追求する姿は、Uターン、移住者であるお二人に共通している視点で、かといって環境の変化や結果に固執しすぎないことも自然だと教わった気がしました。
生まれた作品は、2つとして同じものはなく、その時々の自然を写し出し、大地のエネルギーを感じられる作品となって、日本だけでなく、海外の人々をも魅了しています。

「PREMIO COMBAT 2020 PRIZE」に出品し、ファイナリストに選出された「泥染の布」
北さんの泥染の作品は、イタリアで開催される現代アートのコンペティション”PREMIO COMBAT 2020 PRIZE”にてファイナリストに選出され、展示される予定です。
会場:Museo G. Fattori(Livorno・イタリア)
会期:2020年10月10日〜10月31日
ご自身の経験から、取捨選択をして、自ずとここへたどり着いた北さん。
お話を伺っていて「自然」というワードがたくさん出てきました。自然の美しさを、自然に沿った形で、まるで写真のように、そのままを作品に落とし込む。きっと、まだ見ぬ作品も一貫して、自然が織りなす美を切り取るものであると想像できます。
次はどんな手法で、どこのどんな美しい自然を魅せてくれるのか、期待するばかりです。
文:八木悠 写真:北一浩