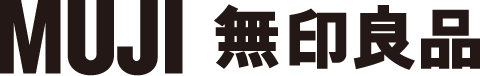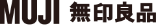栃木県宇都宮市。都心から新幹線で1時間かからないこの街は、商業施設の多さと自然の豊かさが程よいバランスで揃っています。さらに、令和5年には市街地と工業地帯を繋ぐ次世代型路面電車「LRT」の完成も予定しており、街の風景も近未来へと変わろうとしています。
変わらず伝統を受け継ぐ「中川染工場」
栃木県宇都宮市の伝統工芸「宮染め」を生産する中川染(せん)工場は、明治38年創業。J R宇都宮駅の目の前を流れる田川沿いに、当時のままの姿で今も染工場として稼働しています。戦後、高度成長期には、田川沿いに約40以上もの「宮染め」の工場がありました。しかし、バブル崩壊とともに業界は衰退。廃業する工場が増え、現在稼働しているのは中川染工場を含め3社だけとなる中で、伝統を受け継ぎ今も変わらず田川沿いにあり続けています。

時代を感じるノスタルジーな佇まいの中川染工場
「伝統を受け継ぐ」よく聞く言葉ですが、実際には多様なテクノロジーの進化の中で同じ方法を受け継ぐことは容易ではありません。例えば、ひと昔前は音楽を聴くためにレンタルショップでCDを借りてカセットテープやMDに録音して音楽を聴いていましたが、今ではスマホのアプリで音楽を聴くことが主流になり、時代の流れと共にシステムも最新へと変化し続けています。では、なぜ中川染工場は伝統を受け継ぐことを選択したのか。
社長の中川友輝さん(40)にその疑問を問いかけてみました。
中川さん:
「中川染工場では注染(ちゅうせん)いう染め方で手ぬぐいや浴衣を染めていますが、この注染という技術が使えるのは、世界でも日本だけでなんです。しかしプリントの技術が進化し、経営難で廃業する工場が増え、日本でも注染で浴衣を染められる工場は10以下に減ってしまいました。正直、辞めることは簡単ですが、一度辞めてしまったら再生不可能になるのが伝統だと思っています。ノウハウを1から作ることはとても簡単じゃありませんし、道具も今あるものが壊れてしまったら、もう一度道具を作る方法はありません。もし自分が受け継がず辞めてしまったら、これまで続けてきた人に申し訳ないという気持ちもありましたしね」
国体から来訪者に「宮染め」を
10月に開催予定の国民体育大会「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」(略称:国体)で宇都宮市を訪れる選手や関係者に、参加記念品として「宮染め」の手ぬぐいを配布する予定です。
この手ぬぐいは多くの市民協働で制作が進められました。宇都宮市のアパレルセレクトショップとタウン情報誌2社協賛によるデザイン制作、市民によるデザイン投票、中川染工場による手ぬぐい製造、障がい者支援施設による梱包作業や市内中学生による手書きのメッセージカードを添えるなど、多岐にわたる協力で生まれたものです。
デザインは宇都宮市を代表する歴史や文化「黄ぶな」「餃子」「JAZZ」「カクテル」をモチーフにペーズリー柄をベースにした構成で、一般販売も予定されています。
行政、地域企業、市民が一丸となり1つのものをつくり、来県者へ宮染めの手ぬぐいを受け渡すことで、宇都宮市の伝統工芸品を1人でも多くの方に知ってもらう機会となります。これは、地域ブランディングへの架け橋にもなり、こういった働きに対し、多くの市民も自分たちが関わってきたという喜びを感じられ、地域でも伝統工芸に対しての思い入れが広がるでしょう。
また、国体に参加した方の思い出の品として「宮染め」が受け継がれていったら、地域市民として、こんな嬉しいことはありません。
本物の良さをPR「MiyaBiz」
また宇都宮市は、地域資源を生かした地域活性化を目指すため、平成23年にMiyaBiz(ミヤビズ)と称し「宮染め」を活用したクールビズシャツを中川染工場が製造。市長をはじめ宇都宮市職員や議員が「宮染め」のシャツを公務などで着用し、宇都宮市のクールビズのドレスコードとして「宮染め」のシャツが認められました。
そして、マスコミにも取り上げられ県外からの発注にも繋がり、宇都宮ブランドとしてのPRに一役買うことができました。
中川さん:
「浴衣は年に数回しか着ないので、本物の良さを知っていただく機会がどうしても少ないです。その取っ掛かりとして、もっと簡単に着られるシャツを浴衣の生地で作りました。実際に着てもらえればその良さを知ってもらえると思うので」

中川友輝社長(中央)と中川染工場で働く職人さん
父の想いを受け止めて決断、そして苦悩
中川社長は19歳の時、先代のお父様を病気で亡くしました。あとを継ぐかどうか漠然としか考えていなかった中川社長の思いはその出来事を機に、お父様の染め物に対する情熱や、創業から携わってきた人たちの思いを受け継ぎたいという強い意志へと変わりました。
80〜90年代は、プリント技術の進歩が目まぐるしく、それまで日本製が主流だった手ぬぐいや浴衣は、プリントによる大量生産の海外製品が、安価で市場に出回るように。苦しい時代の中でも情熱を注ぎ、伝統を守ってきたお父様の思いは、幼かった中川社長に語られることはなかったそうですが、その姿をずっと見てきたからこそ継承しなければという強い意思に変わったのでしょう。
中川社長が抱える、伝統を受け継ぐための苦悩もあります。それは、先代の時代に多くの工場が廃業したため、技術を継承する職人が激減し、業界自体が衰退するピンチにあることです。今は経営者が工場を存続しようと思っても、継承する職人の不足と、後継者手不足が、伝統を受け継ぐための深刻な課題となっています。
中川さん:
「手ぬぐいや染物に興味を持っている方が、働きたいと言ってくれることもあるのですが、想像より作業はとても地味ですし、工場の夏は暑く、冬は寒いです。それに重いものも持ちますし、水を使うので手荒れもします。手が染料で汚れてしまうことも多々。ですから続かず辞めてしまう方も多いです。ですが、これでも昔に比べて作業を簡素化していて、正直これ以上簡素化してしまうと、伝統工芸ではなくなってしまうので、現状これが限界かと。若い世代の職人を育てていかなければなりませんし、昔は技術を教えず見て覚えろ!でもよかったんでしょうけど、今そんなことしたら敬遠されてしまいますしね。1から10まで教え、雑用や下積みもなく、いきなり染色作業を任せたりしていますが、それでも辞めてしまうんですから、伝統文化って面倒くさいものなんですよね」

田川沿いで染物をする工場がこれからも「宮染め」継承できるように
地域とつながり、伝統工芸「宮染め」を人々に広めていく活動を、情熱を持って取り組んできた中川社長。ですが、職人を育てていく取り組みもまた、経営者としての苦悩なのでしょう。確かに工場は、エアコンの効いた部屋でもなければ、ボタン一つで終わる作業は1つとしてありません。それでもなぜ伝統工芸を残していくのか。
後編では工場内での様子と、注染で染めた「宮染め」の良さをお伝えしていきます。
文・写真:斉藤 純子
リンク:
中川染工場HP