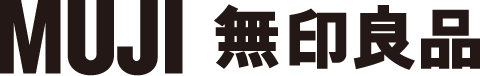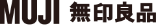ものづくりの町、益子でまちづくり
益子町出身。益子焼販売店「民芸店ましこ」に嫁ぎ、益子の魅力を発信しています。益子町観光協会副会長また益子本通り活性化協議会副会長としてもたくさんの人に会って一緒に益子を楽しんでいます。益子の一番の魅力は人にあり。
栃木県益子町といえば、なにはさておき益子焼でしょうか。
年に2回、春と秋に開催される「益子陶器市」では、人口約2万人の町に多い時には1日約5万人の観光客が訪れ、町中は大賑わいとなります。近年焼き物にとどまらず“ものづくりの町”として藍染や木工、鉄に革製品、竹や服飾、食べ物に至るまで多種多様なつくり手が益子町に集まるようになり、その作品を一同に見ることができる「益子陶器市」は町の一大イベントとして年々発展しています。
しかし、イベントが終了するやいなや、町はいつもの静けさに戻り、穏やかでのんびりとした日常モードへと切り替わるのです。陶器市しか来ない、または日常時にゆっくり来たい、など来訪者が好みの益子を選んで来るようになってきたと感じています。
城内坂通りと本通り
そんな益子町の観光のメインとなるエリアが城内坂通りです。この通りには陶器店が立ち並び、お店ごとに様々な益子焼を見ることができます。1998年に区画整理工事が完了した城内坂の道路は広くきれいに、電柱地中化された歩道は歩きやすくなって現在の風景となりました。人によっては道幅が狭く歩道も無かったかつての風景の方が、趣があって良かったと聞くことがあります。
私が今関わっているまちづくりの対象となる本通りは、前述の城内坂に隣接する益子駅までの、かつて地域の暮らしに必要なものが揃う商店街だったエリアです。駅から順に新町、田町、内町と自治会があり、その昔、田町地区には映画館や役場があり、町一番の賑わいがありました。
しかし、役場の移転や車社会に対応した大型スーパーの出店、後継者問題により閉店を余儀なくされる店舗が増えるなど、いわゆるシャッター通りへと変わっていきました。本通りは歩道が整備されていないため歩きにくく、お店も少ないので、益子駅を降りた観光目的で来た方からは、「途中で不安になってしまった」「今日は閉まっているお店が多いんですね」という声も多く聞かれ、その度に本通りで益子焼を販売している身としては、とても申し訳ない気持ちになります。

益子駅から城内坂手前までの益子本通り地図
土祭(ヒジサイ)を通して
そんな本通りですが、実はポテンシャルが高いんです。それに気がついたのは2009年、本通りを会場に開催された「土祭(ヒジサイ)」がきっかけでした。町と住民が協働でつくりあげる、風土に根ざした地域づくりを目的にした新しいお祭りです。空き店舗や空き地だった場所にアート作品が展示され、その場の空気ががらりと変わったあの時の驚きと感動は今でも色褪せず鮮明に心に残っています。

土祭が行われた現在の本通りの様子
土祭後
土祭が終わった翌年に、商工会主催で「益子本通りの未来をつくる会」が発足されました。土祭をきっかけに、本通り界隈に住んでいる方を中心に、賑わっていた頃の本通りのこと、そしてこれからについて熱く語り合いました。普段は接点のない方と想いを共有できたことはとても新鮮でした。
最初はたくさん人が集まり活気に溢れていた会も、いざ「誰が?」「資金は?」と具体的に進めていくうちに1人、2人と減っていきました。参加者は自分の仕事をしながらの活動とあって、想いはあっても形にするとなると当事者になりづらかったのかもしれません。もちろん、その時の私もまだ幼な子の面倒をみながらの日々で余裕など皆無。パソコンだってまともに触ったことも無く、自分の意見を言葉で表すこともできませんでした。しかし、その時の経験があったからこそ、よりまちづくりに関して興味を持つようになったと思います。
まちづくりに関わってから
その後家族の協力を得て、観光やまちづくりに関する会議・イベントなどに積極的に参加し、たくさんの方に色々教えてもらいました。その中で実感したのは、自分がやりたいことはすぐにはできないということ。まずは与えられたことを当たり前に、面倒なことでも責任を持ってやって、徐々に信頼を得ていき、やりたいことを少しずつやらせてもらえるようになるということでした。
実際に自分の仕事をやりつつ、ボランティアをこなすのはとても大変でした。最初の頃は何でも1人で抱えてしまい夜中まで作業が終わらないことも。その度に何でも自分だけでやろうとせず、周りに協力をしてもらうことも大事だと感じました。自分ができることはしっかりやり、できないことを明確にしてお願いする。何かを成し遂げるには、信頼づくり、繋がりづくりがとても重要だと知りました。
大事な準備期間
現在この本通りでは、益子町実施の「都市構造再編集中支援事業」として、町と地域住民・商工会・観光協会・県内にある宇都宮大学地域デザイン科学部建築都市デザイン学科の皆さんにも協力してもらい、準備段階の2022年から新たな形で活動を開始しています。
私は地域住民代表として声をかけてもらい、今までの想いを胸に参加しています。トータル5年計画の準備期間となる2022年度には、本通りの問題点や魅力、今後の展望等、まずは意見を集める場として“トークセッション”を開催しました。本通りでお店を開業した方をゲストとしてお招きし、「なぜ本通りを選んだのか?」「お店を開くまでの経緯」「本通りの今後」などについてお聞きしています。これまで3回開催し、来場した方の中から本通りで起業したい、移住したいという熱心なオファーをもらった反面、空き店舗でも住居が一体となっているため貸すことが難しい、土地と建物の所有者が違う、等地元住民からの声もありました。
すぐ解決できる問題ばかりではないので長い目で検討していくことも必要です。このトークセッションは本通りに関する意見やアイデアを聞くことができる場として、また、新たな出会いや交流が生まれる場としても継続していく予定です。
2023年度には「益子本通り活性化協議会」を発足し、住民説明会を開きました。今までの経緯とこれまでに出た意見やアイデアをもとに作成した本通りが目指す「暮らす・営む・楽しむ・歩く 多様性のある益子本通り」に基づいた今後の事業計画を説明しました。その後開催したワークショップでは、具体的な実施内容と優先順位を検討し、それらの内容を今後5年間でどう実施していくかを策定し、町へ要望書として提出しました。ここまで関わってくださった方の貴重な意見、また、かつて「未来をつくる会」で出た意見も合わせて、丁寧に時間をかけてこの要望書を作成することができました。
本格始動
2024年からすでに実施しているのがホームページとインスタグラムでの発信です。近年移住した若いメンバーが仲間になり、この活動を継続しています。また、通りにある様々な物の位置関係や建物の調査、空き地の利用方法などを検討、調査してくれるのは宇都宮大学の皆さん。地元の方と多様なスキルをお持ちの方が共に協力することで少しずつ形にすることができています。
益子本通り社会実験クリスマスマーケットの開催
2024年6月には“益子本通りまち歩きワークショップ” を開催して、実際に使うことができるスペースがどこなのか、その場所をどう活用するのかを検討しました。その時の参加者に協力してもらい、陶器市が終わった後の12月にクリスマスをテーマとしたイベントを企画しました。

まち歩きワークショップにて。見慣れた景色も歩いてみると違って見えます
クリスマスマーケットでおこなったこと
①本通りで空き店舗を探している方やこの活動を応援してくれている方が出店
②空き店舗を活用し、まちづくり活動を紹介するブースを出展
③空きスペースの活用(休憩場所、出店場所)
④小学校吹奏楽部クリスマスコンサート
⑤クリスマスをテーマにした大きな絵を描いて会場を彩る
⑥人の動きや流れを調査、アンケートを実施
初めてのイベントのため、どれくらい人が来るのか、駐車場は足りるのか、スタッフをどう配置するか、などとても悩みました。事前の準備に充分な時間を割くことができなかったにもかかわらず、当日は協議会のメンバーそれぞれが適材適所で臨機応変に対応することができ、予想以上の来場者で賑わい、大盛況となりました。

地元学生にイラストを依頼してできたチラシ
益子本通りのこれから
今まで検討して出た内容は、実際にやってみなければわからないことだらけです。昨年のクリスマスマーケットのように成功することばかりではないと思います。今ある課題をトライアンドエラーで時間をかけて解消していき、住む人も訪れる人も快適で楽しく過ごせるように、また、活動を通して賑わいと交流が生まれて魅力ある通りになるように日々活動しています。
益子へ来た際には本通りの活動にも興味を持っていただいて、小さな変化を一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
文:中山久美
写真:村越慧