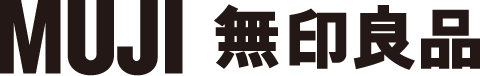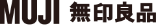光小屋プロジェクト ー未利用材の活用ー
愛知県立芸術大学 美術学部 美術科 彫刻専攻4年。通称”水の”。
大学祭実行委員会での活動を通じて、複数人で一つの企画や作品を作り上げる楽しさとやりがいに魅了される。
その経験をきっかけに、より深く創作の現場に関わりたいと思い光小屋プロジェクトに参加。
この度、愛知万博20周年記念事業として2025年3月25日(火)~9月25日(木)の間「愛・地球博20祭」が愛・地球博記念公園(モリコロパーク)で開催されます。この事業の一環として、「光小屋」に“山の未利用材”を活用したインスタレーションを制作し、現代の山の問題に立ち向かうために「光小屋プロジェクト」が進行中です。
20年前の2005年、愛知県長久手市と瀬戸市で自然の叡智をテーマに開催された「愛知万博」。ここで、太陽の恵みである「光」とともに地球上の生命体が生きていることを表現し、来場者自身もそのことを体験できるドームとして生まれたのが「葉っぱのドーム」です。現在は「光小屋」と名称を変え、万博当時の姿でモリコロパークの中にたたずんでいます。
ここ愛知県には三河地域を中心に広大な森林が広がり、杉やヒノキといった木材を都市で活用しながら、林業が発展してきた歴史があります。しかし近年では、国産材の利用率低下や後継者不足といった問題が深刻化しており、これらは将来的に自然災害や食糧問題など、私たちの生活にも直接つながる課題へと発展する可能性があります。こうした現状を広く知ってもらうために、本プロジェクトは立ち上げられました。
光小屋プロジェクトの活動と山の体験
本プロジェクトは、ライフスタイル商品に自然を取り入れ開発、提供を行う企業・大学生・愛知県庁の産学官が共同して運営し、“森のあり方”・“生き物のこと”を考えながら進められています。それぞれの立場の理念やアイデアを何度も話し合い、コンセプトやデザインを決定しました。アイデアは私たち学生を中心に考え、展示方法や加工方法は企業の力を借り、制作を進めています。
参加企業は、株式会社良品計画、トキワランバテック株式会社、豊田森林組合、西垣林業株式会社、株式会社前田樹苗園、といった山や木を扱う企業で、そのほとんどが愛知県を拠点としています。これらの参加企業の方から、プロジェクトを進める中でのレクチャーで山の現状や課題、取り組みについて深く学ぶことができました。
その中で特に衝撃だったことは、“現代の日本は歴史上もっとも森に緑がある時代と言われていること”です。普段の生活では、森林破壊による地球温暖化のことなどを多く耳にするため、緑は少なくなっているものだと思っていましたが、現実はその逆でした。
なぜ、そんなにも緑が多いのか。それは山の管理ができる人が減少しているためです。「緑が多い」ことにポジティブな印象をもっていたのですが、実際はそうではなく、管理者不足により手入れが行き届かなくなり、過密人工林が増加し、そのために河川の氾濫や土砂崩れ、花粉症、獣害などさまざまな環境問題が発生しているのです。例えば、2000年(平成12年)におきた東海豪雨では、山の環境の乱れが原因で豊田市街地が川の水に呑まれてしまいました。山の環境が崩れることで、川の環境が崩れ、大量の水が街にあふれてしまったのです。
反対に山の環境が整っていれば、河川の氾濫などの災害被害が少なくなるだけでなく、山の栄養が川を伝い、海に流れることで、山や海の生物の環境も整います。美味しい肉や魚、野菜、お酒などは、土や水の状態が良くなければ出来ません。

レクチャーを受ける私たち
これらのことから、私たちの生活は山の延長線上にあると強く感じました。山の環境を整えることは、私たちの暮らしを整えることに直結するのです。
未利用材のインスタレーション
現状をより理解するために、レクチャーだけではなく、山や木の加工現場などを見学しました。そこで目撃したのは木を伐採し、材木となる過程で多くの「未利用材」が生まれる瞬間でした。
・木を伐採するときに、はじめに木に切り込みをいれ、倒れやすくするために木1本に対して必ず1個以上はでる「うけぐち」。
・きれいで長さのそろった丸太にするために切り落とされる「たんころ」。
・木全体が大きく曲がっている「曲り」。
・太さが足りない「小径」。
・丸太を真ん中から四角く切るときに端っことしてでてしまう「バタ」。

山で採取した未利用材たち
これらの未利用材は、製材として使いづらいうえ、市場への安定供給が難しく、活用することが難しいため、山に放置されたり、細かくチップに分解され、バイオマス燃料として利用されたりしています。
未利用材の中には大きなものも多く、それらはお皿や雑貨などを作るには十分な大きさです。そのようにまだ使える素材たちが、一瞬のうちにチップに分解されている様子は衝撃的でした。
未利用材の活用方法を見出せられれば、山の資源を余すことなく利用でき、木材の需要が高まるはずです。しかし、私たちだけで活用方法を考えるのは限界があります。そこで本プロジェクトでは未利用材を使用し、インスタレーションを制作することで、まずは多くの人に“未利用材の存在を伝える”ことを目的にしました。

チップに破砕される小径木
インスタレーションのコンセプトは「光による生命の成長」です。植物は太陽の光のエネルギーを受けて光合成によって成長していきます。種から芽を出し、やがて大きな木へと育っていくその姿は、人間の成長とも重なります。私たち人間も光を浴びて成長し生きる、生命の一つなのです。
太陽の光を感じながら「光小屋」を通り抜けることで、まるで自分が植物になったかのような感覚を味わってほしいと思っています。植物も人間も、成長のカギとなるのは「光」という共通の要素です。このつながりを通じて、山や自然が私たちと同じ生命体であることを実感し、山の課題を自分事として捉えるきっかけになればと考えています。
私たち自身も山を実際に歩き、体験することで山の課題を自分事として感じられました。山の匂いや足が土をふむ感覚、そういった「山の環境」を光小屋に再現することで視覚だけでなく、触覚、嗅覚で体感するインスタレーションをめざします。
「光」と「山の環境」という2つを軸に、未利用材を使用して美しい空間を構成し、訪れた人に未利用材の存在をダイレクトに伝えていきたいと考えています。

コンセプト決定時のアイデアスケッチ
芸術家たちの環境活動
本プロジェクトに参加している学生は愛知県立芸術大学と名古屋造形大学の学生、計5名です。今回のインスタレーション制作の過程で「環境」について強く意識することになり、今までの芸術家たちが環境に対してどのようなアプローチをしてきているのかが気になりました。
廃材で原寸大サイズの動物を作るアーティストの加治聖哉、ドイツのカッセル市に7000本の樫を植えたヨーゼフ・ボイスなどの活動を発見しましたが、特に気になったのはmore treesという団体です。more treesは音楽家 坂本龍一が創立し、建築家 隈研吾が代表を務める森林保全団体で、「都市と森をつなぐ」をキーワードに、「森と人がずっとともに生きる社会」の実現を目指して活動しています。森づくりやそこで生まれた国産材を使って日用雑貨や玩具をデザインし販売したり、森の存在を身近に感じてもらえるような体験の場を作ったり、本プロジェクトと似た理念で活動をしています。
more treesの発起人となった1人に中沢新一という日本の宗教史学者、文化人類学者がいます。彼は20年前の「愛知万博」にも関わっており、愛知万博のテーマである「自然の叡智」を発案しました。彼が提唱した「自然の叡智」は今年開催される愛・地球博20祭でもその意思が継承されています。
光小屋に期待すること
このインスタレーションを通じて本プロジェクトの活動が今回限りで終わることなく、今後も光小屋が「未利用材の活用」に興味を持つ場になることを願っています。
以下は活用の一例です。本プロジェクトの参加企業である製材工場では灰が余っていましたが、この灰は製材で取り除かれた杉の皮をバイオマス燃料として燃やした後に生まれたもののため、純度100%の杉の灰です。もしこの灰が瀬戸や常滑で陶磁器の釉薬として使われれば、愛知県の中で新たな未利用材の活用方法が生まれることになります。このような愛知県近辺で行われている未利用材の活用事例が生まれ、光小屋に展示されることで、環境に優しい技術が広まるような場となればと思っています。
本プロジェクトでは「インスタレーション」という形で未利用材を活用しました。今回の作品やこの記事を通して、多くの人が未利用材の存在に気づくことで、光小屋内では収まらないようなさまざまな活用方法が生まれることを願っています。
インスタレーションを見た方が未利用材をもっと知りたい、そして活用したいと思えるよう、これからも制作を進めていきます。
展示期間は7/13(日)~9/20(土)です。お近くにお越しの際はぜひご高覧ください。
文:水野太貴
写真: 新井亨、水野太貴