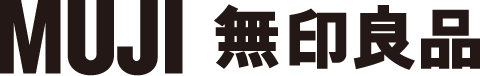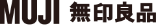春を告げる植物
―雨降り花を摘むと雨が降る―
雪に押しつけられた枯草が地面を覆う春の土手に、霰こぼしのように白い花を咲かせるのはキクザキイチゲ。花茎の先にたったひとつの花をつけて、輪生の葉が両手を広げたようにバランスを取っている。土の匂いの中にかすかな香気が漂う。
雪の下に眠っていたいのちが、本当に呼吸をはじめたと実感させてくれる可憐な花の姿は、待ち望んでいた春の使いだ。わずかな風にも震える花びらを、風を透かすように裂けた葉が守っている姿は、掴まり立ちをはじめた幼子に似ている。
一本の足で危うげに立っているかに見える春の妖精を、「雨降り花」と呼ぶのだと知ったのは五、六歳の頃だったと思う。
裏の土手に白がこぼれていた。待ちわびた春を摘むのは楽しい。両手に抱えきれないほどの花を持って帰った私を見て、父が悲しげに言った。
「雨降り花を摘むと、雨が降るぞ」。
花の名前は知ったが、水に活けてもしおれたまま、ついに生気は戻らなかった。
何か大変なことをしてしまったようだと、おぼろげな不安が胸の内を満たしていたその夕刻から、雨が降った。花が流した涙は朝になっても止まらなかった。雨降り花が泣いたのだと、その夜の後悔は深く心に刻み込まれた。以来、野の花を摘むことはやめた。
雪深い山間の大地がようやく目覚めて吐息を漏らし、一輪の春の使者を地上に送る。
残雪の白を映した雨降り花には、薄く紫が差すこともある。やがて咲くカタクリ、オオイヌノフグリを呼び覚ますように、誘うように、かすかな色を浮かべているようだ。
春の山菜の王者ゼンマイは、雪が残る深い山に渦巻き状の姿を現す。
ゼンマイが好む地形は急峻な山で、採取に入った多くの人が滑落して怪我をしたという経験を持っている。命を落とした人も多い。ゼンマイ採取はまさに命がけの作業だ。
それほどの危険を冒してまでも、なぜゼンマイを採りに山に入るのか。高価な換金山菜だということもあるが、山肌が見えてくると、ゼンマイの姿が目に浮かんでじっとしていられないと話す人も多い。雪に閉じ込められていた半年近い間、ゼンマイに出会うまでの日にちを指折り数えて待っていたのだ。指には綿毛をかぶったゼンマイのつるりとした感触が蘇ってくる。山が呼んでいると感じた晴れた朝、いよいよ山支度で身を整え、山の入り口に立つ。山に踏み入る前に、多くの人が山に対する挨拶と安全祈願のお祈りを欠かさない。
ゼンマイは慶弔いずれの日であっても行事の膳には欠かせない貴重な素材である。神々や祖先、大切な客人をもてなす非日常の膳には必ず添えられる一品だ。大和深く関わりながら生きてきた奥会津の人々にとって、乾燥して保存できるゼンマイは、ハレの日の必需品として生活の基礎にいつも存在し続けてきた。
アクの強いゼンマイは、山から採ってきてすぐに食することはできない。何度も水を替えて煮たら水に晒し、筵に広げて太陽をたっぷりと浴びさせてやわらかく揉む。手のひらでゼンマイを揉む作業を三日間続けなければ、おいしくやわらかくならないのだという。
こうして乾燥したゼンマイは、様々な行事の折々に一年中膳をにぎわしてくれる。

近くの野でも採取できるフキノトウ、コゴミ、セリ、ヤマニンジンなどは、まだ枯れ色の野に散らした緑の絵の具のように、鮮やかに登場してくる。枯草を被っていてもそこだけ光を浴びたように若草色が萌える。枯れ色の野に蘇ったいのちそのものだ。
春の山菜は特にアクが強く、これを適度に摂取することで冬季間に蓄えた毒素をきれいにしてくれるという。
とはいえ、適切な量を知るべしと、山を知り、山菜を知る人たちは必要以上には採取しない。雪に耐えたごほうびとしての恵みの意味を忘れてはいないからだ。
早春の緑の独特のほろ苦さは、積み重ねた人生があればこそ楽しめる味かもしれない。春の若芽はほとんどの種類が食べられるが、春を実感するだけの量を、感謝と共に頂くのが流儀である。
文:奥会津書房 遠藤由美子