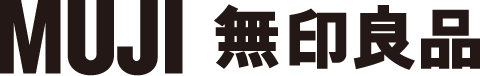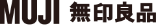神々が住まう山との暮らし ~虫送り~
奥会津には山襞が入り組んだ深い山が多い。数知れない沢が山を走り、出会ってはまた分かれていく。こうしたひとつ一つの沢には必ず名前があり、人々の暮らしの片鱗が残されている。沢の名を知ることは、山での活動範囲を確保することでもある。
神々が座す高み・山に繋がる場所は、そこがたとえ裏の畑であっても、人々は「山サ行ってくる」と言ってヤマジバン(山襦袢)にヤマバカマ(山袴)、二筋手ぬぐいをひょいと頭からかぶって身支度を整え、栽培している作物を採ってくる。畑も地続きで高みの山へ繋がっているからなのだろうか。畑も林も急峻な高みもすべてひと括りに「山」と言い表すのには、そこに共通する神性を見ているからなのかもしれない。そのせいか「森」という言葉を奥会津で聞くことはまれである。
山から流れ来た水で耕す田もまた然り。「田の神」は季節が来れば「山の神」として山へ帰るとも言われるが、「田の神」という名を聞くことなく、その信仰だけは脈々と続いている。
田植えが無事に終わると、家々ではサナブリという行事が行われる。豊作を祈願して、笹餅や笹団子を作って神棚に供える。また、田を耕した鍬や草刈鎌もきれいに洗って飾り、最後に残った稲苗の一束も丁寧に供える。

子供たちが司る弔いの行事
この日の夕刻、村のはずれから、地を這うような低い太鼓の音が響いてくる。何者かが発する原始の雄叫びのように、それは日常の静けさを破ってゆっくりと近づいてくる。音はやがて重く響き渡るほどに近づき、こどもたちの黄色い掛け声も聞こえてくる。虫送りの行列が始まったようだ。
手作りした提灯の揺らめく灯が、暮れなずんだ空から舞い降りた星のように光る。地を這う低い太鼓の響きは、虫を納めた社が発する咆哮のように、低く、重く、地面に響き渡った。
「デンバラ虫の追いくらヨ~イヨイ。よろずの虫も追いくらヨ~イヨイ。」

ゆっくりした掛け声が次第に高くなり、いつのまにか提灯の灯は意外なほど近くにあった。
農耕を妨げる悪虫を送る行事は子供たちが司り、一ヶ月近くかけて準備をする。村内から寄附を募って、行列に加わる幼い子供たちの土産を買い、紙や絵具を買い、手作りの紙提灯に絵を描く。当日の朝、先頭を行く長い青竹を伐り出すのは、中学三年生の男子と決まっている。この日、男子ははじめて大人と同じように腰に鉈(なた)をつけ、鋸(のこぎり)を持って山に入る。山での初仕事は元服の儀式でもある。
子供たちが集めてきた虫たちを入れて祀る社は、午後から全員で草や木で飾り付け、日暮れを待つ。
灯の行列は虫たちの葬列だ。哀調を帯びた掛け声も灯の揺らめきも、幻想的なだけに弔いの哀しみを纏っている。
悪い虫を「退治」するだけなら、こんな行列は要らない。古くから子供たちが伝えてきたのは、虫たちの冥土への道を灯りで照らし、精一杯の荘厳(しょうごん)を手向けて彼らに詫びる気持ちである。いのちを奪うことへの畏れと、恵みへの感謝と、大人たちが丹精する農作物への護りとが、こうした行事を育んできた。知られることもない控え目な灯の行列が繰り返される限り、小さき者たちのいのちを真摯に見つめる精神は失われないだろう。
行事を伝承する意味
奥会津のような山間地の暮らしは、自然や農林業との関わりが深い。自然は、破壊と恵みの極端から極端へ翻る力を持つゆえに、山の神、水神、鳴神など、見えざる神として君臨してきた。「豊かな自然」と平らに均した言葉には、この見えざる神の存在はない。破壊と恵みの両極を司ってこそ自然は健全なのだということを、山の民は骨の髄で識っている。
御し難い自然の力に対しては、人々は身を低め、敬い畏れるしかない。人間の非力さを認める姿勢こそが、人間の奢りを律し、敬虔さや感謝の真の姿を素直に表現する源であった。
これは教わるものではなく、感じ取るもののようだ。様々な自然の脅威に対しての高度な防御策が成され、暗闇もなくなった現代に神々は見えにくくなった。しかし、見えにくくなっただけで「不在」ではないのだということを忘れてしまったのは悲惨なことである。見えざる存在を感じ取る能力が退化した人間は、自らが非力であることも忘れてしまう。
自然から学ぶ最も大切なことは、いのちの有限とその営みのダイナミズムであろう。草木や虫にも人間と等しくいのちがあり、人間もまた有限の生であること。だから慈しみ合えるのだということ。それはおそらく、人間が人間であることの最も本質的な姿だった。それが見えないと、精神構造の成熟した核もなくなるように思う。
真に伝統が伝承されているところには、必ず伝統に貫かれた精神が生きている。そこには、伝承することの意味を感じ取る場があるからだ。奥会津に残る精神の文化は、どこの地域でも探せるものだろう。振り返って自分を探す場はいたる処にある。ただ、そこに至る道が見えにくくなって久しい。
古老の言葉
「山ぶどうの実は、熊の取り分も残しておいてやらねぇとなぁ」
この実は熊にとっても貴重で、そして好物でもある。冬眠のために食料を探し求める熊の立場をわが事のように感じておられる姿勢に、ひそかに敬意を表していた。
ところが、野生の動物を思いやる言葉は色々な方から何度も聞いた。
「この菜っぱは、虫の取り分に残しておくべ」
「トウキビそろそろ食い頃だから、マミ(穴熊の一種)が食いに来る頃だ。まぁ、ちっとはマミにも食わせんなんねぇべ」
「キツネがせつねぇ声でやや生(な)し(お産)だ。明日はふかし飯でも持ってってやんべ」
勿論、大切な作物に対して徹底的に防護策を講じることがほとんどだが、まだこうした思いを大切に抱えている方々がいてくださる。
神々も人間も動物たちも、同じ地面を共有しながら生きている。動物たちも人間も、等しく自然の一部であるという認識から導かれた珠玉の言葉だ。
自然との共生などということはあり得ない。
しかし、自然界での共存は、人間の本来的な姿勢だった。良識などというもの以前の精神生活が、ごく当たり前だった時代はつい昨日のことである。
虫や熊の取り分を考えながら暮らせる豊かさをこそ、次の世代に伝えたい。
文:奥会津書房 遠藤由美子