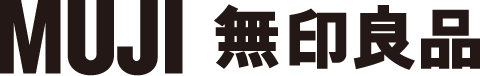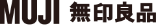日本酪農発祥の地、その歴史がおもしろい
千葉県南房総市在住。編集者、ライター。南房総の里海・里山の自然、つながる人々の豊かさに、胃袋ともども感謝する日々。目下、小規模有機オリーブ栽培に奮闘中。サーファー。2 児の父。
徳川八代将軍吉宗が聖なる白牛の乳からつくった、仏教の涅槃経(ねはんきょう)にも伝わる優れた乳製品“醍醐”の生産を目指したのが、わが国の酪農の始まりと言われています。そして、それら乳牛の繁殖拠点が、千葉県房総半島南部の鴨川市と南房総市にまたがる嶺岡(みねおか)山系周辺に造られた、江戸幕府直轄の嶺岡牧(まき)でした。
お話を伺った鴨川市在住の農学博士・日暮晃一先生が実施する近年のフィールドワークと検証から、遺構の文化が実に多角的につながりをもって見えてきました。
今回は、牛や馬とともに育まれてきた南房総の歴史と文化を、日暮先生の言葉とともに紐解いていきます。

牛や馬を牧内に留めておくための野馬土手。石積みを伴うことが嶺岡牧の野馬土手の大きな特徴のひとつ
原動力生産と防衛要所としての「牧」の役割
日本史上、酪農発祥の地となる嶺岡牧ですが、平安時代から明治時代までは「飼育や繁殖のために牛や馬を放牧しておくための区域」と定義される「牧」として続いてきました。その昔、権力者がいるところには必ず牧があったと言われています。日暮先生によれば、その頃の牧の役割は、原動力となる馬や牛の種畜でした。
日暮先生:
かつて牧は軍馬養成の場であったと言われてきていますが、実はそうではなくて原動力生産の場だったのです。古墳時代の農業革命で農具が木製から鉄製に代わり、農民は犂(すき)を家畜に引かせるようになりました。その原動力として馬や牛は重要な意味を持つようになり、牧はその生産地として経済的に大きな意味を持つようになります。
というのも、嶺岡山系はそもそも石の山で、当時は木が生えても根が浅くすぐに倒れてしまっていました。当然、田も畑もやりにくい。そんな使えない山にも、草が生え、動物がいれば、活用法はあるんです。無価値だった山を、経済的になくてはならない山に変えていったのです。農地として価値がなかったからこそ、そうしたんでしょうね。
江戸時代に入ってすぐ、徳川初代将軍家康は当時その地を治めていた里見氏を改易、大名だった身分が没収されたことで、嶺岡牧は江戸幕府が管理する直轄牧となりました。ちなみに幕府直轄牧は、十一代将軍家斉の時代に静岡県愛鷹に新しい牧ができるまでは3つしかなく、小金牧、佐倉牧、嶺岡牧とそのすべてが千葉県内にありました。
地理的には、小金牧は野田市から船橋市あたりまで、佐倉牧は千葉市から香取市あたりまでに広がり、利根川や水戸街道など要所があった場所に大きな牧が連なっていきました。しかし、嶺岡牧だけは幕府から離れた房総半島南部に位置し、そのうえ広さも佐倉牧のたった1/10にもかかわらず、幕府の目に留まったのはなぜだったのでしょうか。
日暮先生:
嶺岡牧はその当時、どこからでも海が見渡せる場所でした。内房側は鏡ヶ浦(館山湾)とその先の伊豆大島。外房側なら鯛の浦(鴨川市東部)の方角まで。つまり、東京湾への船舶の出入りが全部チェックできる場所だったんです。そんな重要なポイントを家康が放っておくわけがないですね。
江戸幕府の天領だった対岸の三浦半島と並ぶ、当時の海運・海防の要所としても、嶺岡牧は大きな役割を担っていたと言えます。

日暮先生はこれまで一周80キロある牧をすべて歩いて、その遺構をマッピングし続けている
江戸中期以降の酪農業発展における「牧」の役割
冒頭でもお伝えしたように、徳川八代将軍吉宗が最高の薬餌である醍醐の生産を目指し、嶺岡牧に白牛を導入したのがわが国の酪農の始まりと言われていますが、日暮先生曰く、それは将軍個人の嗜好からではなく、国民の健康への配慮であり、吉宗の時代以降も長いあいだ嶺岡牧が国策や社会動向と絡んで発展してきた点を挙げています。
日暮先生:
明治時代になると、欧米と引けを取らぬよう体格を良くして体力を伸ばそうとする富国強兵の流れを受けて、乳牛を生産する地域畜産会社が誕生しました。そして、仔牛が生まれたときに出る余剰牛乳を加工して東京へ出荷するための練乳工場が建ち並びました。
その後、大正時代から昭和前期にかけては、乳児死亡率をゼロにしていこうとする当時の社会動向を受けて、主要製乳企業の工場が立ち並ぶ嶺岡地域が、乳児に必要な栄養素を添加した本格的な粉ミルクの生産拠点となりました。さらに、第二次世界大戦後、学校給食法が発令され、「栄養素を満たす食事を」ということで給食にミルクが必須という規則が定められると、南房総で一手にその生産が担われたのです。嶺岡牧は、長年一貫して国民の健康維持を目標にその存在が引っ張られてきた、他にはないめずらしい牧と言えます。
さて、ここまでの言及から、生乳生産地としての南房総の姿が浮かびますが、それは輸送手段や保存技術が発達してきた明治時代以降のこと。それ以前は、酪農という近代産業の生産手段である「搾乳牛を増やす」ことにポイントが置かれており、その流れから近代酪農の礎がこの地で築かれていった点が興味深いところです。
日暮先生:
「吉宗以降は搾乳牛を生産し始めましたが、牧で搾乳はしていません。嶺岡牧で仔牛を産ませて、母牛と一緒にゆっくり江戸まで連れて行き、搾乳をして、ほぼ一年経ったらまた南房総に戻すということを繰り返していました。
前述のとおり、明治時代に入ってからは牧で発生する余剰乳の行く先に頭を悩ませるようになります。破棄するのはもったいないし、その処理として製乳工場が建ち並んでいったわけです。当時はまだ保存技術的に栄養乳をたくさん生産しても仕方がなかったので、まず加工乳がつくられました。濃度を高めて練乳にしたり、バターやチーズをつくったり。それらの工場がのちのちの明治乳業や森永乳業など、日本の主要乳業メーカーの源流になっていったんです。
他にも、私たちもよく知る国民的乳酸菌飲料の開発が南房総地域の鋸南町で、また乳児用粉ミルク生産の元祖企業が南房総市旧和田町に牧場と工場を運営していた記録があったりと、その遺構はいまも地域のなかにひっそりと佇んでいます。
南房総は、酪農発祥の地であるとともに、酪農近代化の地、さらには主要乳業メーカー誕生の地という側面も持っているのです。

乳児用粉ミルクを日本で初めて開発した和光堂が、生産拠点としていた南海工場に原料を供給するためにつくられた牧場内の牛舎跡
“チッコカタメターノ”は嶺岡牧が育んだ独自の食文化
最近メディアでも話題になったのが、牛の初乳を料理に用いる地の食文化。仔牛が産まれて数日のあいだに母牛が出す、成分が安定しないため市場に出荷できない牛乳が、いわゆる初乳です。昔から酪農家たちの食卓には食材として並んでいました。
見出しにもある“チッコカタメターノ”は、日本語で表記すると「乳っこ固めたぁの」。嶺岡牧周辺地域の方言で、牛乳を固めたものを指す言い回しです。全国的に知られる“牛乳豆腐”という言葉が発生する以前から、この地域では初乳が食されていたので、決まった名前がなく通称でこう呼ばれています。日暮先生によれば、全国の牛乳豆腐文化を遥かに超える多様性を持った初乳の食文化が、嶺岡牧周辺には広がっていると言います。
日暮先生:
チッコカタメターノ料理は現在、レシピが約300種にのぼります。どんどん新しいものがつくられていく、嶺岡牧の生きた食文化です。まだ収集しきれていない地域もあるので、もしかするとその多様性はさらに広がりそうです。他地域には2~3種類しかレシピがないことを考えると、非常に多種多様ですね。
そして、さらなる多様な側面が、乳の固め方のバリエーションです。いわゆる牛乳豆腐は、沸騰する寸前にお酢を入れる方法のみなのですが、チッコカタメターノはいろいろな方法が用いられます。例えば蒸すと、ホエイとして捨てるところがなくなり、すべてが固いプリンのように固まります。加えて、湯煎という方法。さらに冷たいうちに酢を入れるとフワフワの状態ができあがる……というように、これほど固め方にバリエーションのある地域は他にはありません。
もっと言えば、食べる人の多様性もあります。他地域では主に酪農家のみが知る食文化でしょうが、ここでは多くの家庭で食べられていた言い伝えがあります。それだけ乳牛を飼ってる家庭が多かったというのもありますね。「牛を3~4頭飼えば、子供を大学に行かせられる」、そう言われていた時代。いちばん乳業が盛んだった頃で、実に6000戸弱が多かれ少なかれ乳牛を飼っていました。ですので、この地の農家でチッコカタメターノを知らない人はいないくらいです。
この3つの多様性において、「これはもう牛乳豆腐文化ではなく、この地独自のチッコカタメターノ文化である」と言えるのではないかなと私は思っているんです。海沿いは“食べる”という文化を大事にする人が多い傾向で、海岸の文化が入り込んでいると味にうるさいことが多い。だから、チッコカタメターノ自体も好きという人が多くて、実際に食べさせてくれる料理も美味しいことが多いんです。南房総は食材の宝庫なので、それらを全部うまく活かせたらなと思っているんですけどね。

メインになる惣菜からスイーツまで。多種多様な調理法のある嶺岡牧の初乳料理の記録
チッコカタメターノ食は、牧の文化にとってはごく当たり前の側面ですが、地域の人々の暮らしという視点からは非常におもしろい文化です。
実は他にも、石切りの文化が存在し、その端材石が馬土手に有効利用されていたこと、畜産における地域株式会社の仕組みが日本でいちばん最初に誕生した地であること、15世紀末から16世紀にかけてイギリスで起こった近代社会形成の足跡であるエンクロージャー(地主による牧場化のための農地の囲い込み)に似た事象が、極東アジアの小さな牧でも同時期に起こっていたことなど、嶺岡牧は話題の尽きない歴史的遺産です。
小金牧や佐倉牧はすでに市街地として消えてしまい、その全容を解明するのは不可能に近い反面、嶺岡牧の場合、小さな開発はあるもののほぼすべてが現存しているので、いずれ全貌が見える日もくることでしょう。
これからさらに明かされる南房総、ひいては日本史上の歴史的ロマンが非常に楽しみでなりません。

嶺岡牧研究の第一人者である日暮晃一先生の熱のこもった論説は目からウロコの連続だった
文・写真 根岸 功(KUJIKA)