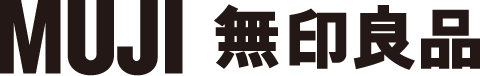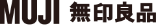未来の里山の在り方を
いきもののいのちで伝えたい
千葉県南房総市在住。編集者、ライター。南房総の里海・里山の自然、つながる人々の豊かさに、胃袋ともども感謝する日々。目下、小規模有機オリーブ栽培に奮闘中。サーファー。2 児の父。
“生き物好き”がこうじて、生き物を調査する環境アセスメント企業から千葉県館山市で地域おこし協力隊の獣害対策担当に赴任した沖 浩志さん。やみくもに駆除されるケースの多い南房総地域の野山に住むイノシシやシカたちのいのちを、“ジビエ”という食のカルチャーを通じて、また“里山”という暮らしのフィールドを通じて、地域の人々にも考えてもらえるようなきっかけづくりに奔走しています。
全国の人口過疎地が直面する共通の課題として、沖さんの獣害対策に対する考え方とその活動についてうかがいました。
獣害対策に関わるきっかけ
沖さんが獣害対策に興味を持つようになったそもそものきっかけは、西日本のとある里山で人と動物との関わり合いを模索する友人の活動からでした。
沖さん:
「会社員時代は、道路やダム建設予定地周辺の生き物を調査する仕事で、生き物と触れ合うというよりも、人工物建造のためにそこに棲む生き物の生態を調べるというものでした。できることなら純粋に、生き物と直接関われる仕事がしたかったんですね。
そんななか、島根で人里に降りて来て人間に危害を与え得る野生の熊を捕獲して奥山に逃がすという獣害対策をやっている友人を訪ねたことがありました。僕と同様、彼も生き物が好きで、「できれば熊を殺さずに山へ戻したい」と言って活動していました。地元の人々からは「危ないから駆除して欲しい」という声も多かった中、しっかり説明しながら続けていくことで、“逃す”という方法に少しずつ理解を示してくれたそうで、うまく対策できつつあるという話でした。そこにすごく興味が湧きました。
その後、研修などを経て、地域おこし協力隊員として、妻の故郷でもある館山市に移住しました。
南房総地域では現状、獣害対象の動物たちは捕獲されたあと、いのちを絶たれてただ埋められてしまうだけのケースがほとんどなので、なんとかしたいという思いがありました。」
いま地域で起こっている獣害の背景には、さまざまな側面があります。
戦後、国内全土に渡って建材供給の目的で植林されたスギやヒノキはその後、安価な輸入材に押されて採算が合わなくなってしまったため、山々は放置され、獣たちの食料を供給できたはずの奥山の餌場が極端に狭まってしまいました。
そして過去、煮炊きや冬の暖を取るための燃料として里山で生産され、重宝されてきた炭も、石油や電気エネルギーにとって代わったため、炭焼きのために人為的に植えられた広葉樹林が野放しにされてしまいました。人が入ることで、奥山の野生の世界と人が住む人里とを緩やかに隔ててきた広葉樹林のある里山にまで、ドングリなどの食べ物を探す獣たちが降りてきて、結果その餌場はさらにその外界である耕作中の田んぼや畑にまで広がっていきました。
加えて、アシやススキなどが生い茂ったままの耕作放棄地は、彼らにとって格好の寝床です。
時代の変化はもとより、地域の高齢化や担い手不足、都市への人口一極化など、現在取り沙汰されている社会問題の多くが獣害とも直接的、かつ複合的に結びついているのです。

鳥獣の狩猟にはいくつかの手法がある。
こちらはイノシシの好物である米ぬかで誘引する檻罠の仕掛け
ジビエで惹きつけ、里山整備で実践する獣害対策
ひと口に“獣害対策”といっても、従事者の考え方によって出口はいくつにも分かれます。
南房総地域では、獣害の指定動物には報奨金がかけられているので、例えば生業のひとつとして猟を行なう方。また畑への被害を減らす目的で罠をかける方。もしくは天然肉や肉の自給など、食や食育という観点から獣を狩る方。こちらは狩猟という概念に重きを置いています。
このように目的はさまざまで、複数の目的や考え方が同居する場合も多々あります。
獣害対策に従事するようになってから1年半余り。沖さんの獣害対策に対する考え方にもたくさんの変化が生まれてきています。
沖さん:
「隊員になりたての頃に市役所の方々と共有していた対策の優先度は、一に“地域づくり”、二に“情報発信”でした。
地域づくりとは、例えば集落単位で狩猟免許取得者を2人でも3人でもまずは増やしていきます。次に、その対策を彼らだけに任せるのではなく、罠の見回りなどできることは被害に困っている近隣の人々も参加してもらうなど、分業体制をつくるというものです。
ただし、いちばんの問題は長期的な意味での高齢化で、動ける若い人たちにも興味を持ってもらわないといけません。
そこで関心が生まれたのが食文化です。“食べる”というのは人間の根元の欲求ですし、食でインパクトを与えられたなら獣害の見方も変わるかなと。
次は、フィールドとなる里山自体に対する関心の醸成。最後に前述した地域の仕組みづくりかなって、この地で対策を推し進めるうちに考え方が変化していきました。
まずは、生き物や里山に興味を持ってもらえるような新しい視点や方法が必要だと感じています。」

くくり罠の仕掛け。落ち葉でカモフラージュしながら獣道に仕掛ける。
BBQとガストロノミーでジビエの魅了を発信
十数年前までは農作物に対する獣の被害も少なかった南房総地域。
もともと海からの恵みが充分にあり、気候的にも食材が豊かなこの地では、野生のイノシシやシカを食べる文化は極めて稀でした。ちなみに九州の中山間地域などは、「爪以外に捨てるところがない」と言われるほど、イノシシが珍重される文化が昔から存在していたといいます。沖さんは最近、そういったジビエ文化を南房総地域全体に根付かせる活動を行なっています。
沖さん:
「季節にもよりますが、イノシシは基本的にメスの肉が美味しく、それに比べてオスは山々を動き回っているのでその肉は少し硬い傾向があり、個体ごとで食味に大きく差が出ることが多々あります。
そこで着目したのがアメリカ式のBBQです。硬い牛肉の塊肉にじわじわ火を通して柔らかくして食べる調理法が現地にあって、それをこの地域内に普及できないかと思い、『南房総バーベキュー協会』という団体を有志で立ち上げました。この地で豊富に採れる野菜なども丸ごとじっくり蒸し焼いて、一歩進んだカタチで日常的にイノシシ肉を楽しんでもらえたら、というのがその狙いです。」

蓋付きのBBQグリルでじっくり蒸し焼くと肉が柔らかく調理できる
もうひとつ沖さんが考えているのが、ジビエとしての南房総地域産狩猟肉のブランド化です。
かつてこの地域は、四国より黒潮に乗って鰹節づくりの文化がたどり着いた場所でした。処理したカツオを燻蒸して乾燥させる行程で用いる薪にナラやシイの木を用いることから、またかつての炭焼きの材料として、幹が堅くて火持ちも良い『マテバシイ』がたくさん植えられました。しかしいま、昔ほどその薪は使われなくなり、房総の山々を隆々覆ったマテバシイが実らせるたくさんのドングリを食べて、いまここのイノシシたちは逞しく生きています。
沖さん:
「メスの肉は本当に美味しいんですよ。ドングリを食べてる時期は脂身も非常に甘く、まさにイベリコです。“ジビエ”という響きに魅力を感じる方は多いと思うのですが、さらにワンランク上の“イベリコ猪”のような打ち出し方ができるのでは、と感じています。
こちらは、日常的に楽しむというより、付加価値を付けてブランド化して提供した方がいいと思っています。
そして、ジビエを使ってみたいというシェフの声も多いことから、『ヒトサラジビエ』というイベントを打ち出し始めました。これは、将来販路になりそうな地域のレストランなど料理店にジビエで数品つくっていただき、お客様を集めてみんなで交流をしながらジビエを楽しもうというイベントです。」
沖さんによれば、南房総地域で捕獲されたイノシシが食肉として有効活用される割合は全体のたった1%ほど、かつ市場に正式に出荷できる解体施設もほぼないことから、ほとんどが自家消費だといいます。そして、99%のいのちは駆除され土に還すだけと、無駄になってしまっています。
狩ったイノシシが何の利用もできないという考えが地域に根付いてしまっている風潮を少しでも変えていかなければならないと、沖さんは語ります。

プロの料理人の知識と創造で生まれたひと皿はやっぱり違う
獣害対策から考える里山との向き合い方
沖さんが考える獣害対策として、ジビエ文化の次に着目しているのが「そもそも獣たちが人里に近寄らないようにするにはどうしたらいいか」を前提に進める里山整備です。
この『ローカルニッポン』でもたびたび取り上げている通り、鴨川の集落で里山の文化を次世代に残そうと知恵を絞る林良樹さんは、毎年『鴨川里山トラスト』の活動を実施して、地元民・都市住民分け隔てなくその文化を伝え、里山に人が入る土壌を守っていく一助を担っています。
また、移住アーティストの有志たちが音頭を取り、アートを手段に里山整備を推し進める『コヅカ・アートフェスティバル』も、もう10年以上、鴨川の中山間部で続いています。
このように現在の南房総地域では、時代に即した新しい方法で里山の整備を手がけるキーマンたちが複数活躍しており、そこへめがけてたくさんの人々が集い、さまざまなタイプの里山のモデルができ始めています。
沖さんが積極的に関わる、南房総市旧三芳村にある2,500坪の里山を持った古民家施設『ヤマナハウス』も、その代表的なモデルのひとつです。
沖さん:
「地域おこし協力隊に着任してすぐ、ヤマナハウスの代表を務める永森昌志さんと出会いました。ヤマナハウスは、分け隔てなく人々に里山での暮らしを実体験してもらう“シェア里山”をコンセプトにしていて、いろんなテーマと里山とを掛け合わせた視点で多角的に里山の利用法を改めて探り、提案しているフィールドです。僕自身、『獣×里山』という掛け合わせを以って、都市住民はもとより、移住者や二拠点居住者の方々に対して狩猟講座などのイベントを主催したりして、がっつり関わっています。
里山を含んださまざまな事象の掛け合わせを通じて、ヤマナハウスを多方面の人々が関わる里山のモデルとして形づくり、そういったものを南房総地域のいろいろな場所につくっていくというのが、里山整備の広げ方としていいのでは、と考えています。
地元の人に話を聞くと、「誰だかわからない外部の人間を突然受け入れるのも、なかなかむずかしい」と聞くので、ヤマナハウスのような外部と内部とを繋ぐ地域のハブができれば、その場所でまず交流した上で、「俺ん家の山だったら、いろいろやってもいいよ」など、段階的にコミュニケーションが深まっていくようなカタチにするのが目標です。
そして、入り口としてシェア里山を経験した人々が移住して、みずから里山に関わっていく。そんな広がりが生まれたらいいなと思っています。
前述の島根の友人のところを案内してもらった際、打ち捨てられた谷などがすでにたくさんありました。その廃墟を見て、「これが未来なんだ」って、ちょっと複雑な気持ちになりました。そういった事象がもう山深い場所では進んでいるんですよね。」

ヤマナハウスで行なう沖さん主催の『はじめての狩猟講座』の様子

さまざまな人々が集い、里山の知恵と実践を共有するヤマナハウス〜シェア里山での活動
人口減少による中山間地域の過疎化に歯止めをかけることはむずかしく、これまで構築してきた暮らしすべてを少ない人数で守り続けていくことは至難の技です。しかし、先人の知恵や育んできた文化、そして人々の暮らしはこれからも守られるべきものであり、守っていきたいものでもあります。
そういった意味において、山に戻す里山、これからも守るべき里山を私たちが見極め、後者に対してもう一度そのケアをしっかりと行なっていくことが、これからの時代の里山への向き合い方なのかもしれません。
獣害対策を深掘りしていくと、私たちがこれから進むべき道が少し見えてくるような気がします。
文:根岸 功
写真:沖 浩志、根岸 功