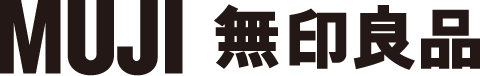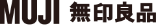盆の灯
8月15日を挟んだ月遅れのお盆には、過疎の町や村にもつかの間の賑わいが戻る。
都会に暮らす息子家族や帰省子が、盆の休みをふるさとで過ごすために帰ってくると、村はにわかに活気を取り戻すのだ。人気のなかった道路には人が行き交い、路上駐車の車が増えてゆく。迎える家族は忙しいが、顔が輝いている。
盆は、一年に一度帰ってくるご先祖を中心に、遠くで暮らす家族が一家に集う華やかな数日間である。雪解けの喜びに芽吹きのときめきや収穫の喜びを重ね、その爛熟期にお盆がある。一年の中で町や村がもっとも華やかなのは、お正月でも祭りでもさまざまなイベントの折でもない。天地いっぱいにいのちが溢れ、生きている人も亡くなった人も共に家の空疎を満たす盆の時期である。自然の営みの最も活発な時期に盆が重なっているのだ。

夏の日盛り。ノウゼンカズラが鮮やかな朱を溶かし、やがて墓前にささげられる盆花が、けだるい暑さの中で匂い立つ。溢れんばかりの野菜はいのちそのもの。空気のけだるささえも盆の華やぎを彩っているようで、ふるさとで刻まれる時の一瞬一瞬がきらめく。
祖霊たちがなつかしい家を訪れ、そしてまた帰ってゆく盆に、あの世とこの世を繋ぐのは、様々な姿をした火だ。
福島県大沼郡金山町と昭和村には、新盆を迎えた亡き人のために「高灯篭」が掲げられる。亡き人が道を間違えずに帰ってこられるようにと、新盆から3年間、家の前に立てられる火の道しるべ。杉の木を十字に組んだ木の先端と横木の先端には、魂のよりしろとして杉の葉がつけられ、横木の中央には「十万世界」「遍照金剛」などと書いた提灯を吊り下げて灯を点し、亡き人の帰りを待つ。遠いあの世から自宅へと辿るはじめての道行はさぞかし不安だろう。高く掲げた灯りを道しるべにして、つつがなく帰って来てほしいという家族の願いは、墓参りの前日の12日か13日の夕刻に灯が点され、暮れなずむ空にあたたかな光を放ち続ける。
十三日の夕刻、庭先で土の竈をつくり小さな迎え火を焚いた後、外出着に着替えたそれぞれの家族が三々五々墓前に詣でる頃は、いつもは人気のなかった往来の人口密度が一気に上がる。亡くなった人たちを迎える人波が行列のように同じ方向に流れて行くからだ。墓のあちこちに立てられたろうそくの灯は、誰も居なくなった闇の中でもまだ燃え続けている。
先祖を迎えた家々の夕餉は、いつもの食卓と違うはずだ。空気を豊かに満たしているのは、子供や孫の顔ばかりでなく、亡くなった人たちのなつかしい振動の響きである。このとき確かに、見えない人たちの存在を実感する。
静かだった日常に徒花のように出現した華やぎは、盆の終わりと同時に姿を消し、胸の中をも吹き抜ける風が秋を引き寄せてくる。ススキを揺らす風が来た道の向こうには、すでに雪の気配が佇んでいるのが見える。
文:奥会津書房 遠藤由美子