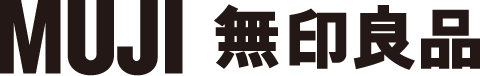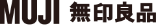一軒の古屋が母たちの長屋になるまで(後編)/ 「つづり」松永レミさんと仲間たち
古民家を改修して営業するカフェやセレクトショップ、ゲストハウス。地方創生の波に後押しされて、古民家活用は、「なんとなくオシャレ」「懐かしくて、新しい」と、観光客を呼ぶ拠点としての役割を担う事例が増えています。一過性のブームのようなものでしょうか。その土地のものを大切にした活動の、土地に根付いた息の長い活動の、拠点となるのでしょうか。
北関東の陶芸の里、益子からのローカルな便りでは、住む人の暮らしの足元から立ち上がっている、古民家というより「古家」を舞台にした、新しい試みについて、前後編に分けてお伝えします。
名前で呼び合う関係から
後編では、母たちが共同でお店を始めるにあたって、言い出しっぺのレミさんが考えてきたことを、さらに3つの視点から紹介していきます。

時間があくと、庭でドングリを拾うレミさん。何に使うかは、記事の後半で。
1つめは、仲間への視点です。玲美さんは母乳育児の勉強会でお世話になった先生の勧めもあり、6年前にお母さんたちに呼びかけ、毎月2回、幼稚園や保育園にあがるまえのお子さんとお母さんで集い活動する「自然育児の会 おむすびの里」を立ちあげています。その活動を通し感じてきたことから、たとえばマリちゃんのお母さんに「マリちゃんママ」などの呼び方はしないという自分のルールをもっているそうです。
「誰々のママではなくて、産んだ人も産まれた人も、ひとりの人として、その人自身を大切にしたいですよね。お母さんの下の名前で呼び合うと、子どもを通して知り合ったとしても、人間どうしのおつきあいとして仲良くなれる。その関係を活動の基本にしています」
帽子や刺し子の制作をしている優子さんは、つづりに参加したことで、気持ちが楽になったと言います。
「手を動かしてものを作る時間、そして、ここに店番で出勤するときは、主婦とか母としてではなくて、自分自身としていられるのが嬉しいんです。家族と一緒にいるときとのメリハリがついて、いい状態でいられます」

さて、母にとっては長い長い、夏を満喫する子どもたちにはあっというまの夏休みが終わり、少し静かさを取り戻した「つづり」の教室スペースでは、恵子さん(CASANE)が主催する「藍の生葉染め」のワークショップが開かれました。
藍は、恵子さんとレミさんが畑で種から育てているそうです。その葉を摘んで洗って、水と一緒にミキサーにかけるところからワークショップでは体験します。

宇都宮市から参加の倉本芙美さん(左)と真岡市から参加で、前編で「作り手の顔が見える商品のよさ」を語ってくれた、日下田すみれさん(右)。
みずみずしい藍の葉をタライで洗います。芙美さんは宇都宮市の民家を借りて、勉強会や手仕事のワークショップを開催するオープンハウスを開いています。恵子さんは、来週には芙美さんの拠点でもワークショップを開催するそうです。長屋のようなコミュニティスペースのような、益子の「つづり」が他の地域のお母さんたちの拠点と繋がっていくことで、また新しい動きも生まれそうです。

何人もの「手」が集まり作業をしながら会話も弾みます。藍の薬効のこと、子どものこと…。「きっと、昔の母たちも、こうやって傍で子どもを遊ばせながら、協力しあって手作業していたんだよね」という恵子さんの言葉に、みんながうんうんと、頷きます。そういえば益子町は、昭和30年ごろまで葉タバコの生産がさかんでした。夏の暑い盛り、タバコの葉を収穫して作業場に持ち帰り、乾燥のための下準備をするのは母や祖母たちが中心だったそう。80歳を超えたお年寄りが「ラジオから流れる舟木一夫にあわせてみんなで歌ったり、いろんな話をしながら手作業していたんだよ。畑仕事ができなくなった近所のおばあちゃんも、この作業なら座ったままできるからって、手伝いに来てくれたもんだよ」と語ってくれたことを思いましました。

藍の液ができたら、持ち寄ったTシャツや布を何回か浸して定着させていきます。自分たちで種から育てた藍で染める。とても贅沢な時間に思えます。


庭にほした麻縄で染めたものを乾かしながら、母たちは、何やら拾い始めます。コナラやクヌギの実です。恵子さんが芙美さんのオープンハウスで行うワークショップでは、これを使った染物の体験を予定しているそうです。かごに半分ほどの自然のめぐみ。恵子さんによると、これで足りる、じゅうぶん染まるだけの量とのこと。ほどよい量のドングリは、レミさんが語ってくれた、お店オープンへの思いにも通じます。
身の丈にあったコミュニティビジネスを
共同でお店を始めたレミさんの2つ目の視点は、経済のことです。
レミさんが千葉から益子に移り住み陶芸の修行を始めたのが20年前。観光客向けのお店が並ぶ道路の拡張と電柱の地中化、歩道の整備などで町の景観がガラリと変わる時期だったそうです。通りに並ぶお店も建物を立て替えて、それまでの昔の風情が残る外観から、どんどん立派になっていきました。
「最初に体験した陶器市は、朝の7時に出勤して夜まで休みなく陶器を売る。とにかく売れるし、忙しくてお昼も食べられないほど。でも、3回季節が巡る頃から、今日は休んでいいよーと言われたり出勤の時間が遅くなったり、夕方の5時にあがれたりするようになって、どんどん景気が悪くなるのを肌身に染みて感じていました」
景気が冷え切ってきても、道路拡張で町を立派にした分、売るための努力はさらに続けていかないといけない。それは益子に限らず、どの地方でも同じこと。レミさんは、作ることへのプライドより、売るための努力が先へいく時代への、漠然とした危機感を感じ始めたそうです。
「背伸びしてものごとを始めちゃったら、それを維持するためにやることが優先されてしまう。お客さんが増えたら、その好機を逃さず、もう1店舗ふやすとか、大きくすることばかりを考える人も多い。大きくすることは誰にでもできるかもしれないけど、そのままでいることのほうが難しい。商売人の家に生まれたわけでもないから、難しいことはわからないけど、生活者の実感として、生きるための経済の基準も加速度的におかしくなっているように感じます。それから、いまの世の中は、経費もほとんどが銀行引き落としでしょ。便利なのだけど。でも、見えないところで進むお金の動きを考えても、本来の、お金とあるものを交換する、という意識がどんどん飛んでしまって、身の丈の暮らしとお金の感覚も麻痺してしまっていくように思えるし…」
とはいえ「つづり」のメンバーでまわす経済のこともしっかりと考えていかなければいけません。なにごとも身の丈にあった考えで、一歩ずつ。その足並みをそろえながら、勉強会や、それぞれの創作活動や、コラボレーションのことなど、ミーティングで顔を揃えて話しあっていくそうです。

藍の青と木の実の色は、手の仕事の色。
庭のドングリ拾いが終わってから、レミさんに3つ目の視点のことを聞きました。仲間への「横」の視点、地域の経済へ「小さくて大きな」視点に続いて、ここで暮らした人達の「過去の痕跡」へのまなざしです。
この古家の先住人たちを、3代前まで遡ると、みんなレミさんが益子に来て知り合った人たちでした。先代は、2004年から昨年の夏まで、ここで開業していた天然酵母のパンと自家焙煎の珈琲のお店を営む高橋さんご夫婦。いまは笠間市に移転して営業を続けています。その前は、都内から益子に移住してきた木や鉄を扱う造形作家の横溝さんご夫婦。そしてその前は、やはり都内から移り住んできた石川さんご夫婦。そして、実はもうひとり。レミさんの気持ちを前に進める上で、大きな役割を果たしたのが、2011年の東日本大震災・福島第1原子力発電所事故の後、いわき市から避難し、縁あって、ここでの仮住まいをしていた、友人・有紀さんの存在でした。祖父母や甥たちもあわせて総勢10人を超える大家族。レミさんは震災後の自分自身の不安も抱えながら、車での送迎などできる範囲で力を貸しました。
一年前に、このふたつの建物が空くと決まった時、最初に饗庭陽子さんが小さい建物のほうで食堂を開くことを決めました。それでは、大きい建物のほうは? 知らない人に借りられるより、これまでの先住人たちの思いや痕跡を知っている者として、自分が引き受けたい。レミさんのお話を伺っていると、その思いに、一番背中を押されたように思います。

横溝創さん作のテーブル。桜などの材を継いで丁寧に仕上げてある。

「まーしこむーしか文庫」は、児童文学のいぬいとみこさんが開いていた家庭文庫を、そのまま綾子さんが譲り受ける形で1996年に開館した。
みんなが集う教室のテーブルは、オープン後に、先々代の横溝さんにオーダーして作ってもらいました。教室の壁に掛けてある陶器の丸いプレートは、3代前の石川綾子さんがここで開いていた家庭文庫「まーしこむーしか文庫」のもので、当時は外から入る木のドアにかけられていました。石川さんご夫妻が町内の別の場所に転居し、新しい家庭文庫が出来たあとも、記念にかけられています。

ドアにかすかな痕跡を残す、プレートのあと。
今年の春には、20年前にこの文庫に通っていたという都内で働く社会人の女性が、お店を訪ねてきてくれました。「土曜日の午後、ここで綾子さんに読み聞かせをしてもらって、ドングリを拾って、本を借りて…、たくさん思い出があります。風の強い日は、家ごと吹き飛ばされちゃうんじゃないかって、みんなで心配しながら借りる本を選んでいたんですよ!」と、建物が残っていることを喜びながら、懐かしそうに話してくれたそうです。
建物を先人の思いとともに引き継ぎ、人と繋がり、小さくても健やかな経済をまわしていく。母たちのチャレンジは、2年目に入ります。
文:簑田理香
【ローカルニッポン過去記事】
一軒の古屋が母たちの長屋になるまで(前編)/ 「つづり」松永レミさんと仲間たち