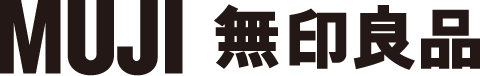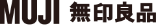川と共にある暮らし
いすみ川とモクズガニ漁
耕すデザイナー。マックブック片手にトラクターを乗りこなす。
千葉県市原市出身。市原市在住。里山暮らし。
千葉県大多喜町からいすみ市を下り太平洋へと流れる夷隅川には様々な生き物が生息します。春はうなぎ、夏は鯉、秋はカニ、季節ごとに様々な生き物が生息し、それに合わせた漁法や食べ方が発展してきました。中でも秋のモクズガニは、近年、漁法や食べ方を知る漁師が少なくなったことから、幻の味と言われるようになりました。夷隅川流域で続けられてきたモクズガニ漁とはどのようなものなのでしょうか。また、そこで営まれてきた川と共にある暮らしとはどのようなものなのでしょうか。9月下旬、旧老川小学校で行われたワークショップ「モクズガニで作る蟹ごし汁づくり」に参加しました。

夷隅川漁業協同組合の高梨喜一郎さん
モクズガニの蟹ごし汁の作り方を教えるのは夷隅川漁業協同組合の高梨喜一郎さん。高梨さんは、高齢化が進み漁師が少なくなった夷隅川流域で、昔ながらの方法で漁を続ける漁師の一人です。高梨さんの家では代々、専業農家としてお米や野菜を作る傍ら、自宅のすぐそばを流れる夷隅川で漁を行ってきました。
子供の頃から川に入り、様々な生き物をとってきたという高梨さん。夏には小学校が終わると皆で川へ行き、ふんどし一丁で飛び込み、手づかみで蟹やエビを捕まえたり、づくしという竹製の仕掛けでうなぎをとって遊んでいたそうです。小学校の水泳の授業も川で行われ、親が田んぼで作業する傍らではタニシやどじょうをとって遊んでいました。このように、川で遊ぶことが日常であった高梨少年にとって、川は危険でもなんでもない場所でした。川は遊び場であり、暮らしの一部だったのです。
農家として暮らしを立てるようになってからも、川と共にある暮らしは続きました。農作業が終わり暗くなる頃、モリ突きに川へ向かいます。カンテラと呼ばれる灯りを頼りに、動きの鈍くなった魚を狙います。フナ、ニゴイ、イセブチ、カワバチ、ナマズ、ハヤ、ヤマベ、とった魚は魚籠に入れ、川を歩きまわります。持ち帰った魚は、囲炉裏のベンケイに吊るし、煙で燻し、保存食にしました。囲炉裏を囲みながらつまみとして食べたり、正月や行事の時には、煮物にして少しずつ食べたそうです。
また、毎年の盆には、“かあがり”という集落総出で行う漁も行われていました。固定網と言われる網を川の下流側に仕掛け、引き網と言われる網を川の上流側から5人がかりで引っ張ってきます。両脇を一人ずつ、深さ2メートル近くある真ん中は2〜3人で持ち、上流から徐々に下流の固定網に向かって引っ張っていきます。徐々に固定網と引き網の距離を縮めていき、最後は網と網の間に追い込んだ魚を、投網や手づかみで捕獲します。一網打尽にした魚は、漁に参加した集落の人たちと分け合い、その日は一軒の宿を決め、とれた魚を皆でいただくのが恒例だったとのこと。お盆に帰ってくる親類も参加するため、とても賑やかで楽しい行事だったそう。

蟹ごし汁づくりは毎年行われる人気ワークショップのひとつ。
ワークショップが行われたのは9月下旬。とれたばかりのモクズガニは、生きたまま会場に持ち込まれました。足を広げると大人の手のひらほどもあるモクズガニに参加者は興味津々。素早く動くモクズガニを手で捕まえたり、恐る恐るつついてみたり。参加者から次々と出てくる疑問や質問に高梨さんは優しく答えます。
モクズガニは、この地域の行事や祭りのご馳走として振舞われてきた暮らしに馴染みの深い生き物です。体長は7〜8センチ、緑がかった褐色の甲羅の両脇には大きな棘があり、ハサミは長い毛で覆われています。ここ夷隅川流域ではモクゾウと呼ばれ、人々に親しまれてきました。9月〜11月、モクズガニが産卵のために海へ下る頃になると、流域の人々は、竹で作ったカニ籠を持ち込み、夷隅川に入ります。
カニ籠は、口にかえしのついた竹製または金属製の籠で、モクズガニをとるのに使います。9月から11月、産卵のために海へ下るモクズガニの通り道に仕掛けます。しかけるのは夕方、下流でとれたボラを餌におびき寄せます。ボラの匂いにつられて籠の中に入り、口のかえしで出ることができなくなったモクズガニを翌朝捕獲するのです。コツはモクズガニの通り道を知ること。一晩で30匹近くとれることもあるそうです。

叩く、潰す、煮る、調理方法はシンプルで豪快。
いよいよ調理が始まります。見本を見せる高梨さんを参加者が囲みます。
まずはモクズガニを捌くところから。逃げ回るモクズガニを手で掴み、まな板の上で甲羅と脚に分けていきます。生きた状態のモクズガニからハサミや脚をもぎとる姿は迫力満点。高梨さんの大胆で迷いのない手つきに参加者から歓声が上がりました。捌いた脚やはさみは出刃包丁を使って細かく叩き潰し、大きなすり鉢に砕いた蟹と甲羅の味噌、そこに白味噌を加え、ごりごりと豪快にすり潰していきます。皆ですり鉢を押さえ、交代交代ですりこぎを持ち替え、滑らかになったら、そこに水を加え目の細かいザルを使って固形物を取り除きます。そうして漉した汁にネギや小松菜にどの青ものを加え火にかけます。火が通ると、すり身が固まり、汁が澄んでいきます。教室に広がる蟹の香りが参加者の食欲をそそります。花が咲くようにふわっと固まったくらいが出来上がりの目安だそう。すり身と上澄みの汁をお椀によそえば、モクズガニの蟹ごし汁の完成です。
同時に仕込んでおいた蟹飯を一緒にいただきました。少ない食材とシンプルな調理方法で作れる味に、会場からは驚きと感動の声が上がりました。

すり鉢、すりこぎ、出刃包丁、昔から変わらない調理道具と調理方法。
そんな後世に残したい食文化も高齢化や後継者不足による問題からは逃がれることができません。夷隅川での漁も、続ける漁師が少なくなりました。誰もが簡単に食料を手に入れることができるようになったためです。かつて、山深い夷隅川上流域では海の魚を手に入れることが難しかったため、代わりにモクズガニやコイなどの淡水生物を獲っては、行事や祝い事のご馳走としてふるまってきました。昔は集落のほとんどの家が漁業権を持っていましたが、現在漁業権を持つ家は、高梨さんの住む集落38軒のうち5軒ほどになってしまいました。

少ない食材と豪快な調理方法なのに繊細で澄んだ味。
また、長い間夷隅川に入り続けた高梨さんは、川の変化にも敏感です。
モクズガニは本来、藤の葉が落ちる頃が食べ頃だと言われてきました。昔は藤の葉が落ちる11月頃に漁を行なっていましたが、近年気温や水温の上昇によりモクズガニが海へ下る時期が早まり、それに伴って漁の時期もどんどん早まっているそうです。また農薬を使うようになったため、川の両側の浅瀬にとどまる稚魚は影響を受けやすいと言います。漁協で産卵場所を作ったり、稚魚を放流しても、大きくなる魚は少なくなってしまったそうです。魚の種類は変わりませんが、それぞれの個体数は明らかに減っていると高梨さんは言います。漁法や食べ方を守ることはもちろんのこと、川やその周りの環境を守ることも必要なのかもしれません。
私たちはいつしか川に背を向けるようになってしまいました。建物は川に背を向けて立ち、子供達を川から遠ざけました。「川は危険でもなんでもない」川と人との距離が近かった時代を懐かしむように話す高梨さんの姿が印象的でした。
10月に起きた台風19号は日本の各地に爪痕を残しました。川の恐ろしさを知ったと同時に、川と人との距離感を考え直す機会になったととらえてもいいのかもしれません。
川と共にある暮らしは豊かです。
自然が猛威を振るう昨今、川に背を向けるのではなく、川と共に暮らす、そんな先人の暮らし方や考え方の中に、未来の暮らしを考えるヒントが隠れているのかもしれません。
写真・文:高橋洋介
リンク:
大多喜町旧老川小学校